丸の内オアゾの5Fにある蕎麦屋「小松庵」。
この店については以前にもちょっと触れたことがあるが、丸の内界隈のそば店の中で私はこの「小松庵」がいちばんおいしいと思っている。
何と言っても、冷たい蕎麦の麺のしゃきっとした洗い方が素晴らしい。
つゆは関東の特徴を備えた濃い口のものだが、極端に「醤油っぽく」はない。
今回私は転勤することになったが、新任地に行くまでの時間がないため「小松庵」で食べることができない。
それでも先ほど挨拶に行って来た。
なんでわざわざ店に挨拶に行くのかと思う方もいるだろうが、急に姿を見せなくなったら「あいつ脳卒中かなんかで倒れたんじゃないだろうか」と思われるかもしれない。少なくとも「元気だけど行けなくなった。もっと通いたいんだけど、やむをえない事情で行けなくなった」ということは伝えておきたかったのだ
ここの若い男性(店長だと思う)に「転勤することになりました」と言ったら、別れを惜しんでくれた。
こういうふうに、店長の感じも良いし、店員の教育も行き届いている。
そして、先ほど書いたように味はもちろんすばらしい。
超おすすめの店である。
January 2008
ショスタコーヴィチには2曲のピアノ協奏曲がある。この2曲は違った性格を持っているが、どちらも若々しく活気あふれた親しみやすいものである。
ついでにいうと、彼にはヴァイオリンの協奏曲とチェロの協奏曲がそれぞれ2曲ある。どれもが2曲ずつということに意味が隠されているのかどうかは解らないが、何かはありそうな気がする。疑い深くて申し訳ないけど……
ピアノ協奏曲第1番(ハ短調Op.35)は、ピアノの他に独奏トランペットを必要とし、オーケストラは弦楽群だけという、コンチェルト・グロッソのような形をとる。
第1楽章はシリアスな調子で始まるが、やがて活気に満ちた音楽が展開される。第2楽章は哀愁を帯びたもの。第3楽章はピアノ独奏による終楽章への序奏のような形で、そのまま突入する第4楽章ははめを外したがっているような騒ぎっぷりである。実に奔放!これがショスタコーヴィチの本質なのだ。
藤田由之氏の解説によると、この楽章にはベートヴェンの「ロンド・カプリッチォ」やハイドンのニ長調のソナタからの引用があるそうで、氏は「聴く者を笑いに誘う」と書いている。けど、私はどっちの曲もよく知らないから、笑いに誘われなかった、残念ながら。つまんないのぉ~。
私が初めてこの曲を聴いたのは木村かをりのピアノ、岩城宏之指揮の演奏でNHK-FM放送によってであった。
この放送の中で、曲が終わったあとに解説者(たぶん渡辺学爾氏だったと思う)が「この終りの方なんかを聴くと、ショスタコーヴィチもなかなかいいもんだと思う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか」というようなことを言っていたのが印象に残っている。
本当に、なかなかいいもんなんです。この曲が書かれたのは1933年。まだショスタコーヴィチは27歳。1936年の共産党からの批判によって「本性」を隠してしまった彼だが(ハロルド・ショーンバーグは、この翌年に「ショスタコーヴィチは1937年の第5交響曲で復権に成功したが、どの点から見ても、彼の作曲家としての経歴は破滅した」と書いている)、実はこんなにウィットに富んだ作曲家だったことが解る。批判以後の、暗い表情をしがちな作品群からショスタコーヴィチを苦手としている人には、ぜひ聴いていただきたい作品だ。
ところで、この作品は彼のチェロ協奏曲第1番変ホ長調Op.107(1959)と形が似ている(ずっとあとに書かれた、チェロ協奏曲の方が似ている、と言うべきか)。オーケストラは通常のものだが、独奏楽器としてチェロの他に、ホルンが独奏的役割を与えられている。第3楽章はチェロ独奏によるもので、終楽章の序奏的性格をもっている。こういう点が似通っている。二卵性双生児ってことにしよう。
ピアノ協奏曲第2番(ヘ長調Op.102)は、1956年から57年にかけて作曲されたが、3楽章から成り編成もオーソドックス。急―緩―急と いう伝統的な形をとっていて、聴いていても古典的かつ簡潔。
第1番は活気あふれる楽しい騒ぎという曲だったが、それでもシリアスさがベースにあった。しかし、第2番は当時モスクワ音楽院に在学中だった息子・マキシムに捧げるために書かれたせいか、全体を通じて温かみのある優しさが貫かれている。
第2楽章の甘い美しさもショスタコーヴィチには珍しいものだし、おどけたように始まる第1楽章は子供っぽい無邪気さを備えている。終楽章は息子の指使いを楽しむかのような曲だ(実際に弾いてみて難しいのかそうでもないのかは私には解らないけど)。この楽章にはハノンのピアノ練習曲からの引用があるという。なかなか気の利いたユ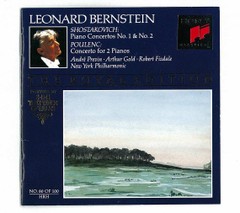 ーモアだなぁ。
ーモアだなぁ。
この曲が作曲された1957年といえば、交響曲第11番が書かれた年でもあるが、その曲との違いはずいぶんと大きい。ショスタコーヴィチ自身が童心に返ったかのようである。
お薦めのCDはソニー・クラシカルのSRCR9535。オケはニューヨーク・フィルで、第1番はプレヴィンのピアノ、指揮はバーンスタイン。第2番はバーンスタインがピアノと指揮を兼ねている。他にプーランクの「2台のピアノのための協奏曲」が収められている(ピアノはアーサー・ゴールドとロバート・フィッツデール)。録音は1959,62年と古い。新星堂にはまだ在庫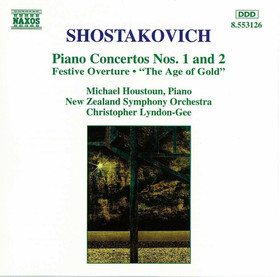 があるようで、2,141円。
があるようで、2,141円。
このCDはレナード・バーンスタイン・ロイヤル・エディションというやたら「・」の多いシリーズの中の1枚。チャールズ皇太子の描いた水彩画が、ジャケットに使われているのである。だからどうしたのって言われれば、確かにどうしたのかなぁと思う。
新しいところでは、ナクソスの1994年録音のものもある(全然新しくないか)。ピアノ協奏曲2曲の他に「祝典序曲」、そしてショスタコーヴィチの若さあふれる機知に富んだ作品、バレエ組曲「黄金時代」が収められている。ピアノはミヒャエル・ヒューストン。リンドンジー指揮ニュージーランド交響楽団の演奏。ちょっと上品な感じの演奏。
あらっ?なぜかラム肉とバンバンジーが食べたくなってきたわ。
キラル(1932- )の「クシェサニ」(1974)。
キラルは映画音楽の世界ではけっこうな有名作曲家らしい。そしてこの曲、なんかすごい曲である。
真面目に書いているのか、相当悪ふざけをしようとし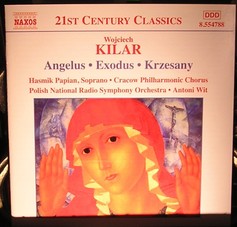 ているのかビミョーな音楽である。
ているのかビミョーな音楽である。
所有しているCDの帯には「ごった煮風の楽想が洪水の如く押し寄せ(音量注意!)モー大変。ポーランドのキラル、いとをかし」と書いてあるが、ごった煮というか、色彩豊かな嘔吐物というか……
とくに最後なんかは単純なメロディーがこれでもかこれでもかと迫ってくる。迫られているうちに、「いやよ、いやよ」が「いいわぁぁぁん」になってしまうのである。
唯一出ていたCDはナクソスの8.554788。「クシェサニ」のほかに、彼の作品が3曲収められている。廃盤になってしまったのかどうかは解らないが、このCDはタワーにも新星堂にもないようだ。
私は聴いたことがないが、別なCDを下に紹介しておくことにする。
あなたも「迫られる悦び」を味わってみませんか?
アランの「芸術の体系」(長谷川宏訳。光文社古典新訳文庫)。
アラン(1868-1951)はフランスの思想家。第1次世界大戦に 従軍中のこの本を書いたという。
従軍中のこの本を書いたという。
内容は「ダンスと装飾」「詩と雄弁」「音楽」「演劇」「絵画」など、全10章と、追記からなる。
とりあえず「音楽」の章を読んでみた。
う~ん。いかにも「思想家」が書いたっていう文章だ。
表現にはなるほどと思わせるものがある。でも、内容については、「ほほうっ!」と膝を打つようなものはなかった(いまだかつて、私は感心して膝を打つなんてことをしたことはない。いまどきいないよね?、そんな人)。
まあ、書いていることは解るけど、そんなに考え込まなくていいんじゃない?っていう感じなのだ。
いや、考え込んでもいいけど、なんだか小難しいのだ。
でも、《すべての情念は自分で自分を激化させるので、音楽はむしろそうした状態からわたしたちを解放してくれるのだが、音楽が情念をかきたてるという言い草はそのことを忘れている。同じような誤解が涙についても見うけられる。涙は悲しみをかきたてるのではなく、悲しみを軽くするものなのだ》(157p)なんて、坊さんの説教を聞かされている様だけど、でも良い言葉だ。「言い草」っていうのもすごいけど……。訳者は考えた末に使ったんだろうけどね。
いま私に突きつけられた課題は、他の章を読む自信があるかどうかだ……
伊福部昭のヴァイオリン協奏曲第2番は、ブルノ・フィルのコンサートマスターを務めていた小林武史の委嘱によって書かれた作品である。
初演は1978年に、コシュラー指揮ブルノ・フィルによって行われ、大好評を得た。
作曲者はこの作品について次のように述べている。
《一個のヴァイオリンと云う楽器がもつ特性を、オーケストラとの対比によって捉え、その協奏を通じて、吾々の血に隠されている感性を問いなおして見たいと考えました。 主要なモチーフには、傳統に近い旋法が用いられています。 と云うのは、作品は民族の特殊性を通過して、共通の人間性に至達しなければならないと云うのが、作者の願いであるからに他なりません。 友人で優れたヴァイオリン奏者である小林武史君に献呈されています。》
この曲は、「ラウダ・コンチェルタータ」(1979)や「交響的エグログ」(1982)と同じように単一楽章であり、曲の構成もA(緩+急)―B(緩)―A’(緩+急)となっているが、曲の雰囲気としては「交響的エグログ」に近い。「気高い寂しさ」のようなものを私は感じてしまう。私は単なる「寂しさ」にさらされているけど……
CDでは、小林武史のヴァイオリン、芥川也寸志指揮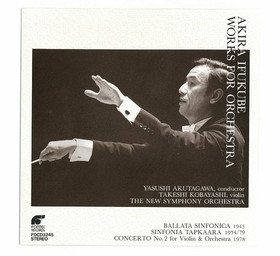 新交響楽団による、1980年4月の日本初演のライブを収めたものが、とても深遠なすばらしい演奏である。フォンテックFOCD2545。現在廃盤。
新交響楽団による、1980年4月の日本初演のライブを収めたものが、とても深遠なすばらしい演奏である。フォンテックFOCD2545。現在廃盤。
現在手に入るCDは、緒方恵のヴァイオリン、井上喜惟指揮アルメニア国立poの演奏。ALTUS-ALT13(2枚組。輸入盤。タワーレコードで2,720円)。こちらの演奏は悪くはないが、何かしゃきっとしないところがある。カレー・ルーが足りないカレーのような感じである。なお、このCDは伊福部昭の「ヴァイオリンとオーケストラのための協奏風狂詩曲(ヴァイオリン協奏曲第1番)」とチャクナボリアンのピアノ協奏曲などが収録されている。
この作品がチェコのブルノで好評を得た背景には、長くドイツに支配されていたために民族的自立を求めていた当地の人々が、伊福部の民族性に立脚した作品への共感を呼んだためと言われている。
なお、スコア(ピアノ・リダクション版)は全音楽譜出版社から出版されている。
♪
ところで、昨日アフィリエイト、特にmixiのことを書いたら、ちゃんとトラックバックで「mixiで金儲けできます」「mixiで金儲け」というのがカモンしてきた(ア・ラ・ルー)。ご丁寧なことに、後者は3つも。しかも、結局行き着くサイトは同じであった。ふ~ん。
それにしてもトラックバックされた記事が昨日の「お小遣い稼ぎは容易じゃないよ」ではなく、ちょっと前に投稿した「『のだめ』人気ってすごい」というのも手がこんでいる。いや、訳がわかんないな。
スティーヴ・ライヒの「ディファレント・トレインズ」(1988)は、聴いていて胸が締めつけられるような作品である。
ライヒは1936年生れのアメリカの作曲家(音楽家)でドイツ系ユダヤ人(あらためて言うことではないのかもしれないが、ユダヤ人というのはゲルマン民族といったような、地域・血統に基づく民族を指すのではない。簡単に言えば、ユダヤ教を宗教とする人々をユダヤ人とかユダヤ民族と呼ぶ)。
ライヒが生まれた年は「ニューディール政策」が打ち出され、ルーズベルト大統領の家系をめぐってユダヤ問題が起こっていた。そんな時代背景のなかで生まれ、さらに複雑な家庭環境に育ったライヒは、脱ユダヤを心がけてみたり、ユダヤ教に戻ってみたりと不安定な動きをしている。
彼はミニマル・ミュージックの手法を開発したが、これは同じ音型・リズムなどを重ねたときに生ずるズレの効果に着目し、できるだけ少数の単純な要素の反復だけから構築する音楽である。
「ディファレント・トレインズ」はクロノス・クァルテットから委嘱されて書かれた作品で、1990年のグラミー賞で最優秀現代音楽賞を受賞している。
曲は3つの部分から構成されているが、それは「アメリカ―第2次世界大戦前」「ヨーロッパ―第2次世界大戦中」「第2次世界大戦後」である(切れ目なく演奏される)。
第1部は、ライヒが子供の頃に、離婚した両親の住まいを訪ねてニューヨークとカリフォルニアを行き来した列車での、付き添っていた家庭教師の言葉やポーターを務めていた老人の言葉などが出てくる。
第2部はナチスによるユダヤ人大虐殺から逃れ生き残った3人の体験談が語られ、第3部はその両方をとりまぜている。
これら「さまざまな列車」について語った言葉が、テープに録音された声によって音楽と一体化する。言葉の抑揚は楽器によって補強され、それがまた言葉にはね返って反復される。これは歌ではない。言葉自体がもつ抑揚が音楽となってしまったかのようだ。
弦楽器は言葉の抑揚をなぞるように同時に重なって演奏し たり、遅れて反復したりする。このようにして「ズレの効果」が生まれてくる。
たり、遅れて反復したりする。このようにして「ズレの効果」が生まれてくる。
曲は、テープに録音された言葉と汽車の警笛と弦楽四重奏に、生の弦楽四重奏が重ねられて演奏される。
CDはクロノス・クァルテットの演奏によるノンサッチWPCS5053のみ(タワーレコードで2,039円)。カップリング曲は同じくライヒのギター作品「エレクトリック・カウンターポイント」(ギター演奏はパット・メセニー。この作品もあらかじめ録音された音と、リアルタイムのギターが重ねられて演奏される)。
それにしても、「ディファレント・トレインズ」で語られている言葉のなかには、何をしゃべっているかさっぱり聞き取れないものもある(いや、そっち方が多いのだが)。実際に、何を語っているか解説の英文をみても、そのとおりに聞こえない。いやぁ、アメリカに住んでなくてよかったぁ。
それから、全然関係ないような、ちょっと関係あるような話だけど、私、昔は鉄道ファンでもありました(鉄道マニアの域に入るのは踏みとどまりました)。
ラヴェルには2曲のピアノ協奏曲がある。
1つは1929年~31年に書かれた3楽章から成るト長調の作品。もう1つは1929年~30年に書かれた単一楽章の「左手のための協奏曲」である。作曲年が重複してるこれら2曲は双子のようなものだ。そして、この双子はラヴェルの最後の大作となった。
ラヴェルはピアノ協奏曲を作曲する際に、モーツァルトに精神的な規範を求めたという。「協奏曲は楽しく華やかであることが重要である」とも述べているが、背景のオーケストラが巨大化し、それに対抗するためにピアノが音を大にして叫ばなくなっていた当時の状況に疑問を抱いたのだろう。
ピアノ協奏曲ト長調は古典的な形式のなか、ジャズ的な要素も盛り込んだ洒落たコンパクトな作品だ。第2楽章は特にモーツァルトを連想させる曲となっている。
一方、左手のための協奏曲は、のちにアメリカに帰化したオーストリアのピアニスト、パウル・ヴィトゲンシュタイン(1887-1961)の委嘱によって書かれた。ヴィトゲンシュタインは第1次世界大戦で右手を失ったが、その後左手だけで演奏活動を行なった。彼の依頼によって書かれた作品としては、他にプロコフィエフのピアノ協奏曲第4番などがある。
この曲、聴いてるだけでは、左手だけで弾いているとはとても思えない。それほど計算された書かれ方をしているということなのだろう。もっともヴィトゲンシュタインは弾きこなすことができず、初演時(指揮はラヴェル自身)には勝手な改変をして、ラヴェルとの関係が険悪になったそうだ。ト長調の協奏曲よりもさらにジャズの要素が多く、ラプソディーのような雰囲気の作品である。
♪
ところで、ピアノ協奏曲ト長調の第3楽章で出てくる旋律が、ゴジラのテーマにそっくりだというのは、知る人ぞ知る有名な話である。
ゴジラを書いたのは私の好きな作曲家・伊福部昭であるが、ラヴェルの旋律に似ているのは単なる偶然らしい。
「9人の門下生による〈伊福部昭のモチーフによる讃〉」という作品がある(ファイアバードTYCY5217-18。たぶん廃盤)。
これは1991年に行われた伊福部昭の喜寿記念コンサートのために、9人の弟子(原田甫、石井真木、眞鍋理一郎、今井重幸、松村禎三、三木稔、芥川也寸志、池野成、黛敏郎)のそれぞれが2~3分程度の小曲を書いたものである。ここで黛敏郎はゴジラのテーマとラヴェルのピアノ協奏曲の該当部分を引用し並べており、その相似がよくわかる。
ゴジラのテーマがオーケストラ作品として書き直されたものに「SF交響ファンタジー第1番」(1983)がある。ゴジラ音楽を重厚なオーケストラによる演奏で聴きたい方にはお薦めである(同第2番、第3番も特撮映画のテーマを使った重厚壮大なオーケストラ曲である)。
お薦め盤は広上淳一指揮日本フィルの演奏のもの(「伊福部昭の芸術 “宙”」。ファイアバードKICC178)。このCDには「SF交響ファンタジー」の1番から3番と、これまた“にんまり”とさせられる「オーケストラと和太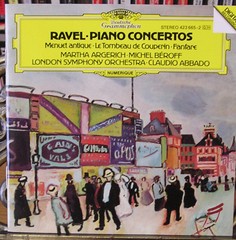 鼓のための“ロンド・イン・ブーレスク”」が収録されている。
鼓のための“ロンド・イン・ブーレスク”」が収録されている。
♪
ところでラヴェルのコンチェルトの方だが、私は ピアノがマルゲリッチ(ト長調)とベロフ(左手)、アバド指揮ロンドン交響楽団のものを愛聴している(グラモフォンPOCG7105)。このCDには私がとっても好きな「古風なメヌエット」も収められている(勝手に言わせておいて)。
だけど、実は黛の曲を聴くまで、ゴジラとラヴェルの相似に気づいていなかった私……。トホホ。
ショスタコーヴィチの最後の交響曲、第15番(イ長調Op.141。1971)。不思議な音楽である。何回聴いても不思議であり、また、切なく美しい曲でもある。
その前に不思議といったら、そうです、昆虫男の話。
この男が、私のランチタイムを台無しにしたこと、つまり買ってきた井泉の「豚丼」を私が上品に食べていたときに、「よくそんなに脂っぽいものを昼から食べられたものだ」と内政干渉、不法侵入、公務執行妨害をしてきたことは、16日に書いたとおりである。
ところが、この男、翌日には自分も井泉の弁当を買ってきて食べているではないか!か!か!カァカァ!
それが果たして「豚丼」なのか「カツ丼」なのか「ロースカツ弁当」なのか、私は確認しようとも思わなかったが、間違いなく井泉の袋をぶら下げて帰って来て、モグモグと食べていたのである(まさか、井泉に「野菜だけでこんなにおいしい!あっさりヘルシー精進弁当」なんてないだろう)。
まったく言うこと、やることなすこと、彼をとりまく全ての空気までが歪んでいる生物である。やれやれ。
ショスタコーヴィチは15の交響曲と、それに対応するかのように15の弦楽四重奏曲を書いている(もちろん明らかに計算ずくである)。
彼の、交響曲としては最後の作品となった第15番は、彼が亡くなる4年前に病床で書かれている。
編成は通常のオーケストラなのだが、それに比して打楽器群が大きい。かといって、オーケストラ全体が強奏する場面は数箇所で、あとは室内楽的な響きが全体を支配する。
この作品は、彼の人生を振り返ったものだと言われるが、なるほどと思わせる。作曲家自身も「そこにはロッシーニ、ワーグナー、ベートーヴェンのそのままの引用が含まれています。多くのことがマーラーの直接の影響の下にあります」と書いているが、マーラーの第9交響曲が作曲者自身の総決算であったのと同様の意味合いがあるのだろう。ただし、ショスタコーヴィチの方がはるかに自伝的である(この曲の第2楽章には、マーラーの第9交響曲の終楽章の引用もある。ショスタコーヴィチが語っている以外にも、こういった多くの引用があるはずである)。
ところで、昨日のマーラーの第9交響曲について書いた文で、私は「この曲はマーラーの交響曲の総決算であると同時に、交響曲の形式の総決算である」と書いた。
でも、そのあとにこうやってショスタコーヴィチは交響曲を書き残している。「この嘘つきめ!」と言いたいんでしょ?そこのあなた。
それはですね、こういうことで手を打ちませんか?
ロシア―ソヴィエトというのは音楽的にもヨーロッパに遅れをとっていた。したがって音楽においても時差があったのである。ヨーロッパにおいて生まれた交響曲という形式は、ヨーロッパにおいてマーラーの時代で終焉したのである。そのあとにももちろん交響曲は書き続けられている。しかし、もはや音楽形式としての本流ではない。エレベーター・ガールのことを「エレちゃん」と呼ばなくなったのと同じようなものだ(エレベーター・ガールという言葉もすでに火葬直前だ)。
第1楽章は、彼のチェロ協奏曲第1番の冒頭を思い起こさせる。楽章中には数回、ロッシーニの「ウィリアム・テル」序曲の断片がでてくるが息子のマキシムはこう話している。「この交響曲第15番は、人間の生涯を回想したものであり、父ドミトリーが少年期にロッシーニの音楽にひかれていて、おもちゃ屋で遊ぶ楽しさを描いている」と。
厭世観に支配された第2楽章。奇妙な出だしで始まる、グロテスクな舞曲のような第3楽章。自らの人生を皮肉な微笑で思い起こしているような終楽章。その後半に低弦で刻まれるリズムは、第7交響曲の第1楽章の「侵攻のリズム」の回想のようだ。そして、最後は彼のそれまでの作品でも顔を出したことがある、打楽器による「ゼンマイがきれていくようなリズム」のあと、星が最後の輝きを放つようにして終わる。
そして、ショスタコーヴィチ自身こう語っている「交響曲第15番には定まった標題はない。漠然としたイメージだけがあって、第1楽章はおもちゃの店で起こるようなことだと言ったことがある。しかし、私がそう言ったとしても、必ずしも正確だとは言えない」。
こんな話を読むと、私の涙腺は緩みっぱなし…。えっ、でも、じゃあ何なの?何が正確なの?はっきり言ってよ。性格悪いよ、って言いたくなるけど。
CDでは、なんと行ってもクルト・ザンデルリンクがクリーヴラ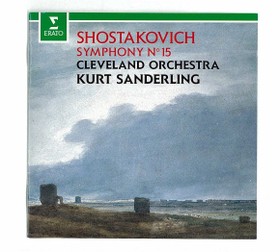 ンド管弦楽団を振った演奏がとにかくすばらしい(1991年録音)。
ンド管弦楽団を振った演奏がとにかくすばらしい(1991年録音)。
でも、ごめん。今は廃盤になってしまった(エラートWPCS5539)。
この演奏では、マーラーの9番(こちらのオケはフィルハーモニア管)との2枚組みCDもあったが(エラートWPCS10833-4)、それも廃盤。でも、哀しいくらい不幸なカップリングだわぁ。
おそらく、これらのCDはそう遠くないうちに再発売になるんじゃないかと思う。根拠は何もないけど。
なお、ザンデルリンクにはベルリン交響楽団を振ったCDもある。1978年の録音で、ドイツ・シャルプラッテンのKICC9471。こちらのCDはタワーレコードに在庫あり。1,800円。この演奏も悪くはないが、クリーヴランド管との演奏に比べると、「あ~ら、ちょっと残念」って感じである(それほどクリーヴランド管の演奏は良いのだ)。
中学生のとき、この交響曲を聴きながら昼寝をしてしまったことがある。目覚めの気分は言うまでもなく最悪だった……
マーラーの第9交響曲は、私の最も愛する作品である。
心無い人はそのことを「ネクラ」だの「病人」だの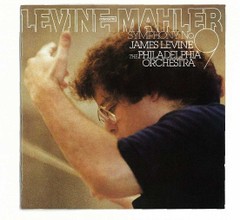 「異常」だのと非難するのかもしれないが、心ある数少ない人は「繊細」とか「感受性が高い」とか「死神と懇意にしている」などと賞賛してくれるだろう。
「異常」だのと非難するのかもしれないが、心ある数少ない人は「繊細」とか「感受性が高い」とか「死神と懇意にしている」などと賞賛してくれるだろう。
よく「もし、無人島で一人で暮らすことになったときに、持って行く1曲は?」という、実に現実味のない、けどちょぴり興味深い質問がある。
数年前までの私は、マーラーの第6交響曲だった。
でも、いまは間違いなく(とも言い切れないが)彼の第9交響曲である。とはいえ、第6番も捨てがたいけど……(ほらね、煮え切らないでしょ?)。
「大地の歌」の最後は“ewig”という言葉が消え入るように歌われる。「永遠に、永遠に…・・・」である。
そして「大地の歌」の次に書かれた第9番は、短い序――この冒頭は“Amen”と歌われているように思える。私は何かに取り憑かれているのだろうか?――のあとに、この“ewig”の旋律が切なく優しげに現れる。
これだけで涙もの。年をとると涙腺がゆるくなって困ってしまう。
第3楽章では第3交響曲の“パンのテーマ”が回想される(変型されているが)。
終楽章では、「大地の歌」の終楽章「告別」に出てくる“小川の音”も現れる。
第2楽章はマーラーが好んだレントラーだ。
この曲はマーラーの交響曲の総決算であることは勿論のこと(軍隊ラッパ風のファンファーレだってちゃんと第1楽章に出てくるし)、交響曲という音楽形式の総決算でもある。この曲で、交響曲という形式は終焉を迎えたのだ。
私は理屈ぬきで、深い感動を覚えてしまう(って言うわりに理屈っぽいけど)。
「バビ・ヤール」のブログのときに書いた、通販のレコード店。
私は大学生のときに、ここからレヴァインがフィラデルフィア響を振った、この曲のLPを買った。それまではワルター盤を聴いていたのだが、実のところあまりこの曲は心に入ってこなかった。心を閉ざしていたわけじゃあないのに。
しかしながら、若いレヴァインの演奏によっては、私はこの曲の魅力に目覚めた。英語で言うならWake up やぁ~。
このレヴァイン盤を聴き続けていたとき、ちょっぴり悲しい出来事があった。
当時、私には付き合い始めたばかりの女の子がいた。彼女は東京出身で、理由はよく解らないがわざわざ北海道の大学に入学したのだった。顔は見栄晴君に似ていた。向こうから付き合ってほしいと言ってきた。
2月のある日の午後、私は学校に試験の成績発表を見に行った。
その前に彼女は「発表を見た帰りに私のアパートに寄って。その日はずっといるから。待っているわね」と言っていた。
学校に行った帰り、2月にしては大粒の雪が降る中、私は教えられた彼女が住むアパート“モモンガハイツ・堤川”に行った。変な名前だ。学生の飛躍、滑空、野生化の祈りを込めているのだろうか?
チャイムを鳴らす。
部屋の中で何かが動く気配はない。死んだように昼寝をしているのだろうか?
もう一度鳴らす。
ドアの向こうで「ピンポーン」と、はかなく鳴るだけだ。
『もしかすると私が来るから、急いでコンビニにおもてなしの飲み物を買いに行ったのかも知れない。少し待ってみよう』と、根拠のないプラス思考で、しつこい新聞勧誘員、あるいはねちっこいNHK集金人のように、私はドアの前に立っていた。
ちょうどその時、変なおばさんが通りかかった。
「ここに何か用事?」
「はい」
「留守なんじゃないの?あなたお友達?でも、あんまりうろうろしないでね」
あとから解ったのだが、私のことを変な奴と思ったこの感じの悪い変なおばさんは、この変な名前がついたアパートの大家さんだった。つまり堤川夫人である(未婚かも知れないが)。
それにしても、ひどい女だ。
人に寄ってと言っておいて、出かけているとは。
これもあとで解ったことだが、彼女はかなりいい加減な人間であった。何かにつけてだらしがないのである。
ついでに言うと、彼女とは1ヶ月ぐらいですぐに別れた。彼女から「やっぱり別れましょう」と言ってきたのだ。いったい何が「やっぱり」なのか、さっぱり意味不明である。
付き合ってくれだの別れてくれだの、まったく身勝手だ。付き合ってくれと言われてから別れてくれと言われるまでは、ずっと春休みだった。だから私は彼女に嫌われるようなことは何一つしていない。だって、彼女は東京に帰省していて、まったく会ってないんだから。
こんな純情な男の気持ちをもてあそぶなんて、どうしようもない奴だ。解ってんのか、見栄晴!
無駄足を踏んで、腹がたつやら空しいやらで、雪道を駅に向って歩いたときに、ずっと頭に流れていたのはマーラーの9番の第2楽章だった。悲しきレントラー、ってか?
以上、だから何を言いたいんだよ、っていう話を終わる。
レヴァインはこの頃、マーラーの交響曲を次々と録音していた。1番や5番、6番もすばらしい演奏だが、この9番がいちばん成功しているかも知れない。
録音について言えば、LPのときには、高音になるとキンキンしていたが、CD(RCA-BVCC38137~38)になってそれが少し良い方向に抑えられているように思う。
いまはレヴァインのCDは廃盤のようだ。
ただ、マーラーの9番は良い演奏のCDがたくさんある。作品の完成度が高いせいなのかしらん。
それにしても、何がモモンガだ!
ヘッセの「車輪の下で」。光文社古典新訳文庫。訳は松永美穂。
この小説も、私は今になって初めて読んだ。ヘッセってなんだか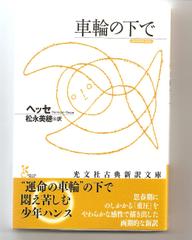 かたそうでつまらなそうだったから。
かたそうでつまらなそうだったから。
結論。面白かったです。
物語は《周囲の期待を一身に背負い猛勉強の末、神学校に合格したハンス。 しかし厳しい学校生活になじめず、学業からも落ちこぼれ、故郷の町で機械工として新たな人生を始めたのだが……。 地方出身の一人の優等生が、思春期の孤独と苦しみの果てに破滅へと至る姿を描いたヘッセの自伝的物語》というものだ。
う~ん、私の人生とは似ても似つかぬものだ。ドイツに生れなくてよかった(っていう問題じゃない)。
優等生の挫折ということで思い出すのは、村上春樹が「ノルウェイの森」で書いている文だ。
阿美寮で直子と同室のレイコさんが、かつてピアノの生徒として教えることになった中学2年生の女の子の話だ。
レイコさんはこう話す。
《……結局のところその子はきちんとした訓練に耐えることができない子なのよ。世の中にはそういう人っているのよ。素晴らしい才能に恵まれながら、それを体系化するための努力ができないで、才能を細かくまきちらして終わってしまう人たちがね。私も何人かそういう人たちを見てきたわ。最初はとにかくもう凄いって思うの。たとえばものすごい難曲を楽譜の所見でバァーッと弾いちゃう人がいるわけよ。それもけっこううまくね。見てる方は圧倒されちゃうわよね。私なんかとてもとてもかなわないってね。でもそれだけなのよ。彼らはそこから先には行けないわけ。何故行けないか?行く努力をしないからよ。努力する訓練を叩きこまれていないからよ。スポイルされているのね。下手に才能があって小さい頃から努力しなくてもけっこう上手くやれてみんなが凄い凄いって賞めてくれるものだから、努力なんてものが下らなく見えちゃうのね。他の子が三週間かかる曲を半分で仕上げちゃうでしょ、すると先生の方もこの子はできるからって次に行かせちゃう。それもまた人の半分の時間で仕上げちゃう。また次に行く。そして叩かれるということを知らないまま、人間形成に必要なある要素をおっことしていってしまうの。これは悲劇よね。……》(下巻13p)
この文は、凄いと思う。教訓のように語られているが、見事に核心を突いている。「ノルウェイの森」という小説のなかでも、特に注目に値する文章だと私は思っている。謎とき本では取り上げられることはないが(謎じゃないから)、すばらしい視点だと思う。
「車輪の下で」の主人公、ハンス・ギーベンラートは、こういった人間とはもちろん違う。彼は一生懸命に努力して神学校に入学できたのだから。しかし、努力したゆえに、夢を果たせなかったことがかわいそうだ。「ザマーミロ、この高慢ちき野郎」とはならないのである。なぜハンスの人生が狂ったかは、各自読むように!
松永氏の訳はとても流れが良い。私がヘッセに抱いていたかたいという印象が払拭されたが、それも訳のすばらしさのせいであろう。
この小説では自然描写もすばらしい。たとえば第2章の最初から描かれる野草の花の様子なんかは、自分が山道を散策しているように思わせてくれる。
《ヘッセ研究で知られるフォルカー・ミヒェルスは、『車輪の下で』が日本でドイツの十倍もよく読まれていると述べ、その理由として、日本の学校における厳しい競争原理を挙げている》と訳者は解説のなかで触れているが、確かにそうなのかも知れない。
さて恒例の、この本のなかで私が最も気に入ったフレーズ(いつから恒例?)。
《そもそも貧しい人々の子どもというのはやりくりしたり節約したりする方法を知らず、いつも手許にあるものをすべて使ってしまって、とっておくことができないものだ》(106p)
すいません。私もそうです。そのとおりです。とっておくものもないんです。
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
- 12音音楽
- J.S.バッハ
- JR・鉄道
- お出かけ・旅行
- オルガン曲
- ガーデニング
- クラシック音楽
- コンビニ弁当・実用系弁当
- サボテン・多肉植物・観葉植物
- シュニトケ
- ショスタコーヴィチ
- スパムメール
- タウンウォッチ
- チェンバロ曲
- チャイコフスキー
- ノスタルジー
- バラ
- バルトーク
- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽
- バロック
- パソコン・インターネット
- ピアノ協奏作品
- ピアノ曲
- ブラームス
- プロコフィエフ
- ベルリオーズ
- マスコミ・メディア
- マーラー
- モーツァルト
- ラーメン
- ルネサンス音楽
- ロマン派・ロマン主義
- ヴァイオリン作品
- 三浦綾子
- 世の中の出来事
- 交響詩
- 伊福部昭
- 健康・医療・病気
- 公共交通
- 出張・旅行・お出かけ
- 北海道
- 北海道新聞
- 印象主義
- 原始主義
- 古典派・古典主義
- 合唱曲
- 吉松隆
- 名古屋・東海・中部
- 吹奏楽
- 周りの人々
- 国民楽派・民族主義
- 変奏曲
- 多様式主義
- 大阪・関西
- 宗教音楽
- 宣伝・広告
- 室内楽曲
- 害虫・害獣
- 家電製品
- 広告・宣伝
- 弦楽合奏曲
- 手料理
- 料理・飲食・食材・惣菜
- 映画音楽
- 暮しの情景(日常)
- 本・雑誌
- 札幌
- 札幌交響楽団
- 村上春樹
- 歌劇・楽劇
- 歌曲
- 民謡・伝承曲
- 江別
- 浅田次郎
- 演奏会用序曲
- 特撮映画音楽
- 現代音楽・前衛音楽
- 空虚記事(実質休載)
- 組曲
- 編曲作品
- 美しくない日本
- 舞踏音楽(ワルツ他)
- 行進曲
- 西欧派・折衷派
- 読後充実度
- 邦人作品
- 音楽作品整理番号
- 音楽史
- 駅弁・空弁
© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」

