えっとぉ~、ブルックナーの交響曲を紹介するのは、今回が2回目だったかしら?
いやだわぁ、アタシったら最近とみに物忘れしやすくなって。
ちょっといけてないレコード・ショップ「ぴぴ」。札幌の西野にあったこのお店のことは、何度かお話ししたわよね?覚えてる?
ここはアタシが通っていた学習塾のすぐそばにあったのね。だから、時おり立ち寄ったものよ。
とてもとっても小さい店。ネコが9,600匹も入ったら足の踏み場もなくなっちゃうんじゃないかしら。
でもね、店の狭さとは反対に、店員のお兄さんはとってもアゴが長かったわ。関係ないって?でも、折りしもアゴいさむの人気が高まっていたころなのよ。トレンデーだと思わない?
そんなお店だから、置いてあるクラシックのLPはせいぜい5~60枚ってとこ。
あらっ、いやだぁ~。違うわよぉっ!
5枚から60枚ということじゃないのよ。50枚から60枚ということ。う~ん、勘違いしないでよ、いい大人なんだからさぁ。
そんな数少ないLPの中に“交響曲第4番「ロマンティック」”というのがあったの。このタイトルに惹かれたわ。 この交響曲の作曲者はアントン・ブルックナー。
この交響曲の作曲者はアントン・ブルックナー。
アントニオ猪木とかゼットンとかとは関係ないの。そしてね、このときが、アタシとブルックナーとの出会いの日になったの。
そう言えばアタシとマーラーとの出会い、だから“交響曲第1番「巨人」”のLPを買ったのも、同じようなシチュエーションだったわ……。その日も店員のお兄さんのアゴは長かったわよ。「アゴだけ巨人」なんてね。
アハ、アハ、アハ、アハッ!おっかしいでしょっ?
マーラーにもブルックナーにも、アタシったらこうやって「ぴぴ」で出会ってるのよね。素敵なお店ね、「ぴぴ」って。
ブルックナーって、マーラーと一緒に語られることが多いの。2人ともオーストリアの作曲家だし、同じ時代の交響曲作曲家として。しかも、1960年過ぎから、人気が徐々に高まってきたというのも共通よ。
でも、実は2人の音楽ってずいぶんと違うの。ブルックナーは1824年に生まれているの。
あら、やだっ。
もう気がついちゃったの?そうなのよぉ。ブルックナーはマーラーより36歳も年上なの。そして、オルガニストだったの。オルガニストって、教会でオルガンを弾く人のことよ。興奮している人のことじゃないわよ。
作曲面ではワーグナーの影響を受けて、ワーグナー流の大きな管弦楽と大きな楽想展開による交響曲を書いたのね。でも、すっごく評判が悪かったの。今でもブルックナーの交響曲は、嫌いな人はとにかく嫌いみたいよ。「退屈だ!」って。その気持ちもわかるわ。
そんなブルックナーは自分の交響曲を何とか演奏してもらいたいものだから、ずいぶんと改訂をしたのね。もう、ズッタズタ!「演奏してくれるなら、どうなってもいいわ、アタシを好きにして」って感じよ。
今では、原典版、つまり改訂前の楽譜で演奏することが多いんだけど、その原典版すらはっきりしてないの。いったいどれがオリジナルなのかしら?、ってね。
ハース版だとかノヴァーク版とかいう楽譜があるんだけど、これはハースという人や、ノヴァークという人が校訂した“原典版”。だけど、同じ原典版と銘打っているこの2つの楽譜でさえ違いがあるのよ。「元祖・豚丼[E:pig]」というお店がたくさんあるのと同じ感じよね。しかも、例えばノヴァーク版でも第1稿とか第2稿とかがあるの。節操がなくてイヤよね?
どの楽譜を使うかは指揮者の考え方だし、さらに他の版を使う場合もあるわ。
さっき、ブルックナーはワーグナーの影響を受けたって言ったでしょ?知ってるかしら?ワーグナーに対抗する当時のもう1つの流れはブラームスだったってこと。ワーグナー派とブラームス派があって、ブルックナーはワーグナー派に色分けされていたの。でも、ブルックナーはワーグナーの音楽に惹かれていただけで、ワーグナーと親密な間柄にあったわけじゃ全然なかったのよ。まあ、派閥争いに巻き込まれたのね。
だから、ブラームス本人やブラームス側の立場にいた有名な批評家・ハンスリックに、ずいぶんと悪口を書かれたらしいわ。あらためてブルックナーの交響曲と比べてみると、ブラームスの交響曲ってすごい保守的な音楽よね?だから結婚できなかったんだわ。関係ないかしら?あっ、でもブルックナーもロリコンだったわね。
あるとき、オーストリア皇帝がブルックナーに「何かしてやれることはないか」と尋ねたというの。そしたら、なんて答えたと思う?
「はい、ございます、陛下。ハンスリック氏に、あんなひどい事を、私について書くのをやめるよう、おっしゃっていただくと大変ありがたいのですが」ですって!
おっかしいでしょ?皇帝にお願いすることじゃないわよね?オホホホホ。おなかがよじれちゃうわ。もう、ブルちゃんたらぁ、って感じよね!
マーラーが学生の時にブルックナーの講義を受けたという証拠はないの。師弟関係もなかったわ。ブルックナーの講義に一度は履修登録したんだけど、そのあと抹消されているっていうの。きっと、マーラーは「受けるのや~めた」と思ったのね。でも、大失敗に終わったブルックナーの第3交響曲の初演の場には居合わせたの。
聴衆の大半が演奏の途中で帰ってしまうという状況のなか、マーラーは最後まで拍手を送り続け、失意の作曲者を支持しようとした1人だったのよ。感心よねぇ~。このときマーラーは17歳。セブン・ティーンよ!ブルックナーは感謝をこめて、この曲の自筆総譜をマーラーに贈り、それはマーラー家の家宝になったそうよ。美しい話ね。
とはいえ、その後、指揮者・マーラーはブルックナーの交響曲をそれほど多くは振っていないのよ。男の世界って不思議よね。
ブルックナーは1番から9番までの9曲の交響曲と、番号なしのヘ短調のもの、それに自分で0番と呼んだ交響曲があるの。0番はヌルって呼ばれることもあるわ。そして、番号なしのは00番、ヌルヌルって呼んだりもするの。おっかしいわよねっ!
つまり全部で11曲。そして最後の9番は未完。
きゃっ、いやだ!怖~い!マーラーと一緒よ。マーラーも1番から9番までと、番号のない「大地の歌」、そして未完の10番。ねっ?11曲になるわ。いやだぁ~、アタシもう1人で眠れないわ!熱帯魚でも飼おうかしら。
でも、マーラーとブルックナーの曲はずいぶんと違うのよ。マーラーの曲は各楽器がソロ的に扱われるけど、ブルックナーではあまりそういう感じがないわ。音楽評論家のショーンバーグが言ってるけど、マーラーの曲は時には聴き手に狂気を作り出すけど、ブルックナーの場合は狂信的な心酔を呼び起こすんだって。
オルガニストだったブルックナーの交響曲は、パイプ・オルガンのような響きがするとも言われているわ。確かにそうだと思うの。そして、信仰の篤いブルックナーにとっては、音楽は神を讃えるためのものだったのね。バッハみたいじゃない?そう思わない?マーラーとは違うわ。
女性はあまりブルックナーを好まないって言うけど、そんなことはないと思うわ。私は好きよ。えっ?あなたはオカマだろって?お黙り。
やだ、アタシったら!太い大きな声をだしちゃった。ごめんなさいぃ~。
どっちにしろ、ちょっと聴いてみてくれる。でも、退屈って思うかも。進行がゆっくりしているから。
私も一度、コンサートでお尻が痛くなって難儀したことがあったわ。あら、やだっ!難儀だなんて、まるで年寄りみたいね。
「ロマンティック」のことだけど、すっごくホルンがソロ的に活躍するのが素敵よね。曲の最初っから、なんていうの、深い森を思い起こされるわ。スコアを載せてみたの。その最初のところよ。このスコアは音楽之友社から出ているものだけど、第2稿ノヴァーク版よ。
前にコンサートでスコアを追いながらこの曲を聴いてる、ちょっといただけない人を見たの。私の席の斜め前でちょうど見えたの。でも、途中からうまく追えなくなって首をかしげているの。きっと演奏されている版と持ってきたスコアの版が違ったんだと思う。
みっともないわよねぇ~。
§
本日は、私のお知りあいである、自称オカマのケティちゃん風に書いてみました。口調は若 い頃の桃井かおりに似ています。
い頃の桃井かおりに似ています。
◆ 補足
ブルックナー(Anton Bruckner 1824-96)の交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック(Romantische)」WAB.104の「ロマンティック」という名は、各楽章に中世ロマネスク時代への憧れを示す標題的内容があるということで、作曲者自身がつけたものである。
楽譜には、大まかに、第1稿=ノヴァーク版第1稿(1874)、第2稿=ハーズ版&ノヴァーク版第2稿(1878-80)、レーヴェ改訂版がある。
◆ 蛇足
今日はあえて朝比奈隆やヴァントではなく、ブロムシュテットがドレスデン・シュターツカペレを振ったDENON盤をご紹介しておく(1981年録音)。使用している楽譜は第2稿ノヴァーク版である。
October 2009
いわゆる前衛音楽である。当時はバリバリの前衛だったことは間違いない。
でも、いまになって聴いてみると、むしろお茶目な感じさえしてしまう。
ジェルジー・リゲティ(Gyorgy Ligeti 1923-2006)の、100台のメトロノームのための「ポエム・サンフォニック(Poeme symphonique)」(1962)。
その名のとおり、“楽器”はメトロノーム。しかも100台。 100台のメトロノームを一斉に鳴らす。
100台のメトロノームを一斉に鳴らす。
やがてゼンマイが切れ、1台、そしてまた1台と止まっていき、最後は1台だけがカツカツ、カツカ…ツ、カ…ツ…カ……ツ…、…カ……ツ……、カ…………ツ、………カ…………、という具合に“曲”は終わる。
100台のメトロノームを同時に鳴らし始めるのは不可能に近い。私が持っているCDでは100台が元気良く揃ってギャラギャラギャラギャラともダダダダダダとも、なんとも形容しがい音で鳴り響いている状態から始まっている(録音風景の写真はCDのライナーノーツから。整列鎮座しているメトロノームがなんとなくかわいい)。
そして、鳴っているメトロノームが減り始めると、その時々で様々な不思議な表情が現われてくる。最後は「ご臨終です」という心音停止を連想させる。
これは電子メトロノームじゃだめだろう、きっと。
微妙な速度のズレがたぶん出てこないだろうから。
いや、もしかしたら同じような効果が出るのかも知れないけど(電池が弱ってきたらテンポも狂うのかどうか、私にはわからない)、ゼンマイの具合で衰えていく音がなければおもしろくない。
ところで、リゲティは1956年のハンガリー動乱ののちにオーストリアに亡命し、ケルンの電子音楽スタジオでシュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen 1928-2007)たちとともに制作活動を行なった前衛音楽の作曲家である。メトロノームによる「ポエム・サンフォニック」はもちろん電子音楽ではなく、演奏のたびに異なるものとなる偶然性音楽と言える。 これが収められているCDは「リゲティ・エディション第5弾」というもの(1995年録音)。
これが収められているCDは「リゲティ・エディション第5弾」というもの(1995年録音)。
「ポエム・サンフォニック」の他には、バレル・オルガン(自動オルガン)用に編曲されたリゲティの作品が収められている。
ちなみに「ポエム・サンフォニック」でメトロノームを“演奏”しているのは、テリューという人である。
「ベートーヴェンがある夜散歩していると、一軒のあばら家から自作曲が流れてきた。中をのぞいてみると、盲目の少女が月光の中で弾いている。『一曲弾きましょう』とベートーヴェンがあがりこんで弾き始めるうちに、たちまちすばらしいメロディーが浮かんできた。ベートーヴェンは弾き終わるとあわてて家に帰り、それを五線譜に書き写した。それがこの曲で、『月光』の名の由来である」。
ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827)のピアノ・ソナタ嬰ハ短調Op.27-2「月光(Mondschein)」の誕生秘話である。
何と美しい話であろうか!
ただし、これが本当の話なら!
でも、はっきり言わせてもらおう。こんな話はウソである。
だいたい、ベートーヴェンのような恐い顔した男に家の中をのぞき見され、そのうえ勝手に部屋に上がりこまれたら、「きゃぁぁぁぁ、ケダモノぉ~、お願い許して!」と恐怖におののくはずだ。少女が盲目だったからベートヴェンはまだ救われたのだとも言える。
それに「あわてて家に帰る」というのも滑稽だ。
ロマンティックで感動的な出来事のあとに、あわてておウチに帰ったのだ。
あの顔で夜道を猛速で歩行されたら、相当怖い。
実は「月光」という標題は、詩人レルシュタープが第1楽章を形容して「スイスのルツェルン湖の月光にきらめく波間に漂う小舟のようだ」と言ったことに由来しているらしい。
もしレルシュタープが第1楽章よりも第3楽章に関心を寄せ、「地球に接近する妖(よう)星ゴラスのために、絶望の危機に瀕している人類のパニック状態のようだ」と言ったなら、このソナタは「妖星」と呼ばれていたかもしれない。
ごめん、はずした?
まあとにかく、これが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタの中で、他人が命名した最初のソナタである。
この曲は発表されるとたちまち人気をよんで、とかく文学的に解釈されてきたらしいが、ベートーヴェン自身はそれを苦々しく思っていたという。
伯爵令嬢ジュリエッタ・グイチャルディに献呈されているが、彼は当時この少女に心を奪われていたらしい。曲は3つの楽章から成るが、全曲が続けて演奏される。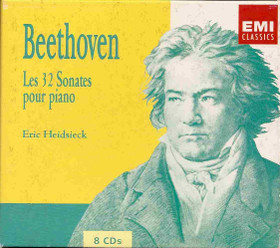 今日はハイドシェックの演奏によるCDをご紹介(EMI。ピアノ・ソナタ全集で録音年は1967~73。掲載写真は旧盤のもの。現在は下のようになっているよう)。
今日はハイドシェックの演奏によるCDをご紹介(EMI。ピアノ・ソナタ全集で録音年は1967~73。掲載写真は旧盤のもの。現在は下のようになっているよう)。
この演奏がどうこうよりも、ハイドシェックにはちょっとした思い出がある。
今から30年ほど前、札響の定期でハイドシェックがベートーヴェンの「皇帝」を弾いた(指揮は朝比奈隆)。
曲が終わるとなかなかの喝采。
ところが2~3度のカーテンコールのあと、自分の腕時計を指差して(演奏中も腕時計をしてたのだろうか?それとも最初に下がったときにステージの袖でつけてきたのだろうか)、そそくさと帰ってしまった。
きっと飛行機の時間があって、あわてて家に、ではなくて千歳空港に向ったのだろう。札幌に泊まってジンギスカンでも食べりゃあいいのに。
みんなみんな、東京さ行ってしまうだ……
という思い出。ねっ、全然たいした思い出じゃないでしょ?
朝の通勤。なんとなく気分がのらないときに聴くと、あまり考えないでもけっこう元気づけられるのがチャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-93)の序曲「1812年」変ホ長調Op.49(1880)である。
この曲、大序曲とか荘厳序曲とか祝典序曲とか呼ばれることもあるが、ただの「序曲」でいいんじゃない?って私は思っている。まあ、原題に忠実に従うなら「荘厳序曲」ってことになるようだけど。
この曲は1812年のナポレオンのモスクワ遠征の失敗を描いたものである。この歴史的事実については、村上春樹の「海辺のカフカ」にも出てくる。カフカ少年が高村図書館でこの出来事が書かれてある本を読むのだ。
ナポレオンの大敗北から70年後の1882年にモスクワで全ロシア産業芸術博覧会が開かれたが、序曲「1812年」はその祝典音楽として作曲された。チャイコフスキーはこの式典のために曲を書くのは、その経緯からも気が進まなかったようだが、結果的にはポピュラーな名曲となってしまった。
冒頭で合唱によって歌われるのはロシア国歌である、と思っていたらどうやらそれは私の勘違い。このメロディーはリムスキー=コルサコフの歌劇「クリスマス・イヴ」でも用いられているのだが、正教会の聖歌「神よ汝の民を救い」だという。
ずっと勘違いしていました、私。
「クリスマス・イヴ」(この曲はとっても素敵!ただ、私が知ってるのは組曲版のみ)について書いた過去記事でも「ロシア国歌」と書いてしまっているが、ごめん、あれ間違いだから、と開き直り。
この聖歌やナポレオン軍を象徴する「ラ・マルセイエーズ(La Marseillaise)」、ロシア民謡にロシア帝国国歌「神よツァーリを護り給え」のメロディーが絡み合い、最後は“大砲”が鳴り響く中、勝利を祝うようにロシア国歌が高らかに奏される。
「ラ・マルセイエーズ」はルジェ=ド=リール(Claude Joseph Rouget de l'Isle 1760-1836)が1792年に作曲した曲で、1795年にフランス国歌に制定されたもののナポレオン3世時代には他の国歌が用いられた。1879年に再び採用されている。また、ロシア帝国国歌は1833年に制定されている。
つまり実際の1812年の時点では、ロシア帝国国歌はこの曲でなかったことになる。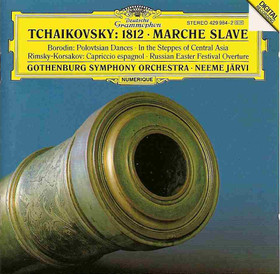 私の愛聴盤はヤルヴィ指揮エーテボリ響、同合唱団、エーテボリ・シンフォニー・ブラスバンドによる演奏(グラモフォン。1987年録音)。
私の愛聴盤はヤルヴィ指揮エーテボリ響、同合唱団、エーテボリ・シンフォニー・ブラスバンドによる演奏(グラモフォン。1987年録音)。
いやらしいぐらい大太鼓の音がすばらしい!
ところで全音楽譜出版社のこの曲のスコアにある園部四郎氏による解説に、以下のような記述がある。
《なお祝砲には、実際に大砲をぶっぱなすことになっているが、演奏会では、むろん大太鼓で代用される。ただしイギリスの水晶宮での演奏では、実際に大砲をぶっぱなしたということである。また大砲の音を使ってふきこんだレコードもある》
ぶっぱなす……
ヤルヴィ盤でもぶっぱなしてくれてます。
でもなぁ~。朝、気分がのらないのって毎日だからなぁ。毎朝、大砲を聴き続けるわけにはいかないしなぁ……
いやぁ、私のPCに明らかに架空請求と見られるメールが来た。
アップルシステムというところから。
実はその1週間前にも同じメールが届いていた。
送信者のアドレスはランダムなアルファベットの文字列。そこで、サーバーから削除するように設定したのだが、また別な英文字列でお届きあそばした。
もちろんまったく心当たりはない。
それでも最初に「重要なお知らせ」というタイトルで次のようなメールが届くと、少なくともハッピーな気分にはなれない。
貴方が御利用になられ
た有料サイトの使用料金
が今だ確認できません
。すでに御精算の期日
が超過しています。こ
のまま御連絡や御精算
の確認が取れない場合
は、日に日に料金が加
算されていきますので
、大至急御連絡下さい。
※03-3546-8050
【サイト管理担当竹内】
なお、本日15時までに
御入金の確認が取れな
い場合は、メールアドレス、携
帯端末番号等、様々な
独自の方法で、携帯電
話の請求書元に裁判通
知書をお送りさせて頂
くことになりますので
、必ず営業時間内に御
連絡下さい。
※メールでのお問い合わせ
は一切行っておりませ
ん。
【電話対応時間】
平日9:00~19:00
03-3546-8050
【サイト管理担当竹内】
アップルシステム
こういう非日常的な変化が起こると人間というもの、少しは動揺する。
それは滅多に行かない、例えば食べ放題のクリスマス・ディナーコースなんかで、おだってしまったあまりに、いきなり手前に置いてあるナポリタンやら焼きそばやらサンドイッチを皿に取って食べてしまい、早々に満腹になり、奥の方のローストビーフや伊勢えびのグリルの存在に気づいたときには何も口に出来ない状況に陥っている、というのにも似ている。
だからこのメールを見たとき、おだちはしないまでも、少しは考えた。
何かしてしまっただろうか、と……
でも、ほれほれ、冷静に考えなさい。
奥のローストビーフのことを思い出しなさい。
まず、このメール、PCに入ってきているのに、体裁は携帯メールのものだ。
仮に携帯でサイト利用したとしても、メールは携帯に入るのが自然。散弾銃方式ってわけね。
第2に届いた時刻は15:03分。15時までに支払うのはどう考えても無理。やっぱり散弾銃方式で発信しているのね。
サイト名も書いていないし……。いったいどんなサイトだぁ?
メールではなく電話で問い合わせろって、明らかに電話番号を探り出そうとしている。
“アップルシステム 架空請求”でネットで検索してみると、まったく同じ文章が紹介されていた。電話番号も竹内という名も同じ。
やれやれ、有名なメールだったのね。
皆さん、気をつけましょうね!
でも、送信アドレスをランダムに変えてくるから、とってもめんどい。文字列の@以降を拒否指定するとyahooメールのすべてが拒絶されちゃうしね。
いたちごっこってことか……
アップルシステムは不滅です、ってかぁ。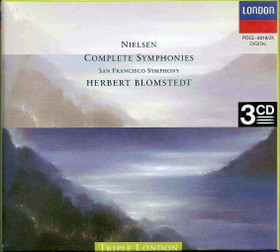 ということから、本日はデンマークの作曲家ニールセン(Carl August Nielsen 1865-1931)の交響曲第4番Op.29,FS.76「不滅(Det uudslukkelige,独:Das Unausloschliche)」(1915-16)。
ということから、本日はデンマークの作曲家ニールセン(Carl August Nielsen 1865-1931)の交響曲第4番Op.29,FS.76「不滅(Det uudslukkelige,独:Das Unausloschliche)」(1915-16)。
この交響曲は4つの楽章から成るが、楽想としては4つの楽章が密接につながっているので単一楽章の曲として扱われる。
第1次世界大戦という恐ろしい状況の中で生命の不滅を訴えた曲で、ニールセンの代表作でもある。「不滅」という標題は「消し難きもの」などと訳されることもある。
激情、素朴、強靭といった音楽が織り交ぜられているが、最後の楽章は2群のティンパニによる競演が印象的。
私が持っているCDはブロムシュテット指揮サンフランシスコ響による演奏(デッカ。1987年録音)。あまり他の演奏と比較したことがないが、この演奏は整っているという点で名演奏。ただ、もう少し暴れてもいいんじゃないかと感じる人もいるだろう。
なお、ニールセンの作品につけられているFS.番号は、Fog&Schousboeによる1965年出版の作品番号である。
大学生のときの友人だった須藤君。
彼の特技は、しばしば英語で寝言を言う、というものであった。
といっても、覚醒時にはまったく英語が話せない。
英語のテストの成績はものすごく悪かった。
彼はテストのときにカンニングを試みたこともあったが、それでも点数をとれなかった。
それなのに英語で寝言をいうことが何度かあった。
ということは、特技ではなく憑依という方が正しい。
なぜ私がそのことを知っているかというと、彼は学生寮に住んでいて、その同室の人間から聞いたのだ。
英語ができない人間が、ペラペラとそれも無意識でしゃべっている姿は、まるで壁に飾ってある鹿の頭の剥製が笑い出すくらいに(そういう羨ましくない豪華な家に私は実訪問した経験はないが)相当気味が悪かったという。
で、須藤君の神秘性をさらに決定づけた、もう1つの事件があった。
やはり寝言である。
彼は夜中にいきなりコブシを挙げて「この異教徒め!」と叫んだことがあったと
いうのだ(それは日本語で)。
英語……。異教徒……。
同室の人間が怖がるのも無理はない。
英語の寝言をしゃべったという件については、もしかすると聞き間違いじゃないのか、という笑い話になり得る。というのも、同室の奴も須藤君に勝るとも劣らず英語ができなかったからだ。彼が英語だと思って耳にしていたのは、実は英語なんかじゃなくてフランス語かイタリア語だった可能性もあるわけだ。
ただ、外国語に聞こえていたものが、もしかするとお経だったりしたら、マジに怖い。眠りながら宗教戦争を繰り広げていたわけだ、須藤大師様は。
その後須藤君は、今度はアムウェイにはまってしまった。
アムウェイで稼いで、インドに修行に行こうとでも目標設定したのだろうか。
でも、少なからずのケースがそうであるように、アムウェイはしばしば周囲の者のを困惑させる。
須藤君も我々を困惑させた。
私たちは大学生なのだ。
どれだけすばらしい性能、効能であろうが、洗剤や洗浄パワー増強剤は必要ないのだ。
卒業後、私は彼と一度も会っていない。
宗教とアムウェイ、どちらかの方向に彼は向っていったのだろうか?
それにしても、須藤君はどこでアムウェイなるビジネスを知ったのだろう。
それもまた謎のままだ。
須藤君は何度か私の家に遊びに来たことがある(私は自宅から通学していた)。 彼が遊びに来たときにマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第7番(ホ短調「夜の歌(Lied der Nacht)」。1904-05作曲)の終楽章を聴かせたことがある。「ドンドコドンドン、ドンドコドンドン、ドンダァー、ドンダァー」とティンパニの力強い独奏で始まるやつだ。
彼が遊びに来たときにマーラー(Gustav Mahler 1860-1911)の交響曲第7番(ホ短調「夜の歌(Lied der Nacht)」。1904-05作曲)の終楽章を聴かせたことがある。「ドンドコドンドン、ドンドコドンドン、ドンダァー、ドンダァー」とティンパニの力強い独奏で始まるやつだ。
クラシックにはまったく興味のない須藤君だったが、この「ドンドコドンドン」には目を輝かせた。改宗の空気でも感じたのだろうか?
彼は数日後にはマーラーの7番のCDを買っていた。
どの演奏が良いかといったアドヴァイスを私に一切求めることもなく……
失礼な奴だ。
そのとき聴かせたのはマズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏(ドイツ・シャルプラッテン。録音は1982年。写真は旧盤のもの)。マズアという指揮者、私にはどこかつかみどころのない演奏をする人に思える。生でブラームスを聴いたこともあるが、良く考えてみると、もしかしたらベートーヴェンだったかもしれないというくらい、記憶が曖昧になっている。
このマーラーの第7は悪くない。
ホント、悪くはない。破綻もきたしていない。
でもワクワク感欠乏症候群になりかけている。 ひどい言い方をすれば、ちょっとドン臭い。それがドイツ・シャルプラッテンの残響の多い録音と相まって、“角界力士オールスター400mハードル競争”のような感じになっている。
一時期はこの演奏ばっかり聴いてたんだけどな……
マズアの演奏解釈はともかくとして、残響の多い音造り(録音)がこの録音では裏目に出ているのかもしれない。個人的にはこのレーベル、けっこう好きなんだけど……
 新聞によると、コレステロールや中性脂肪の値が高い人の方が脳卒中を起こしにくく、発症した場合も状態が良いとのデータが、東海大学の大櫛陽一教授によってまとめられ発表されたという。
新聞によると、コレステロールや中性脂肪の値が高い人の方が脳卒中を起こしにくく、発症した場合も状態が良いとのデータが、東海大学の大櫛陽一教授によってまとめられ発表されたという。
脳内出血、くも膜下出血でも脳梗塞と同様に、高脂血症の未治療の人の発症リスクが低く、治療している人のリスクが高かったという。
全国にいる、私と同じように中性脂肪の値が高く、医者に叱られ、家族に罵られ、生保の切り替え時には嫌味を言われ、高い薬代を払っている同志よ!
何と素敵な研究結果だろう。
私は中性脂肪の薬のほかに、痛風防止のための尿酸の薬も朝晩飲んでいるが、痛風だって一説によると食事とはあまり関係ないらしい。ビールや肉なんかは良くないと言われてきたのに、こうやって180度話が違ってくることだってあるのだ。
数年後には、尿酸の値が上がらないように、肝やレバーをビールをお伴に積極的に食べましょうと言われているかも知れない。
アタシ、誰を信じたらいいの?
さて、くも膜下出血で亡くなったとされる作曲家に、メンデルスゾーン(Felix Mendelssohn(-Bartholdy) 1809-47)がいる。
1847年の5月に姉のメンデルスゾーン=ヘンゼル(Fanny Cacilie Mendelssohn-Hensel 1805-47)が急死した。彼女はピアニストで、ピアノ曲や歌曲など400曲の作品も残しているが、健康だった姉が突然意識不明となって、わずか4時間で亡くなった。脳卒中だと言われている。
その報を受けたメンデルスゾーンは大きなショックをうけ、うつ状態となったが、さらには躁状態になる。
10月になって手の麻痺症状が現れ、さらに激しい頭痛に襲われる。
治療には蛭(ヒル)が使われた。蛭に悪い血を吸わせるという当時の治療法である。
10月28日の午後には神経卒中だと医師が診断した発作に襲われる。異常な興奮状態になったがこれは回復する。
その2日後の30日に弟のパウルが見舞いにきた。11月3日までは弟と会話をしていたが、3日に会話している時に倒れ意識不明となる。そして11月4日の夜に亡くなった。
最近の研究では、メンデルスゾーンも姉も、脳卒中で死ぬには若すぎるので死因は別にあるとされている。また、嘔吐がなかったり途中意識障害などもなかったため、くも膜下出血でもないと推察されている。
結局は死因は謎に包まれたままである。
§
メンデルスゾーンは「無言歌集(Lieder ohne Worte)」というピアノ曲集を8巻書いている。
無言歌というのは、歌詞を持たない歌曲風の旋律を持つ小器楽曲。各巻とも6曲から成る。
第1巻Op.19は1832刊、第2巻Op.30は1835刊、第3巻Op.38は1837刊、第4巻Op.53は1841刊、第5巻Op.62は1844刊、第6巻Op.67は1845刊、第7巻Op.85は1850刊、第8巻p.102は作曲者の死後刊(出版年はいずれも各巻の全曲版のもの)である。
各曲にはタイトルがついている。
例えば第1巻の第1曲は「甘い思い出」、第2曲は「後悔」、第5曲「眠れぬままに」。第2巻の第2曲「慰め」、第3巻第2曲「失われた幸福」、第4巻第3曲「胸騒ぎ」、同第4曲「心の悲しみ」etc.etc…(お気づきのとおり、ここではあえてネガティヴなタイトルばかりをご紹介!)。
ただし、これらのタイトルのすべてがメンデルスゾーンによるものというわけではなく、出版の際に便宜上つけられたものの方が多い。いま、ここで紹介した7つのタイトルも、実はすべて作曲者によるものではない。
ここでは田部京子が弾いたCDを。抜粋盤で25曲が収録されている。1993年録音。
実はこのCDを聴いていると、なぜかわからないが私はすごく居心地が悪くなる。
演奏のせいではないと思う。これまた謎だ。
何かこの演奏でお気づきの方、いらっしゃいませんか?
CDラジカセによる大雑把な再生ではあまり感じないので、微妙な音揺れなのかな……
ただ、CDジャケットの写真の色合いが気に入っている。
小学校のときの全校朝礼で、その日の朝、校長先生が校庭に残されていた野糞を発見し、その憤懣やるせない感情を児童全員と共有しようという目的で話されましたとさ、ということを書いたのは数日前のことだ。
そのブログを読んでくれた私の愛読者(そういう気高い人たちをムゥネリアンと呼ぼう)の1人と酒を飲んだら、その方はご自分の悲しき体験を教えてくれた。教えてくれたということは、書いてくれ、その憤懣やるせない感情を世間の皆さまと共有したい、という野望を抱いているとうことだろう。だから書くことにする。
その人の名をここではとりあえずエリザベートということにしておこう。
その人が若い頃―これで、この人が現在は若くないことが推察されることとお喜び申し上げます―のことだが、ある日の朝、ゴルフに行こうと自分の車のところへ行くと、まぁ、なんということでしょう、ボンネットにはウンコがてんこ盛りになっているではありませんかっ。
そのウンコはどう考えても一人のものとは思えないボリューム!匠のサービス精神が伝わってきます。
ということなのだそうだ。“不快ビフォー・アフター”である。
しかも、ボンネットにそのように盛られているということは、当然そこに上がってしゃがんでしなくてはならない。果たしてそのとき、フロントガラス側を向いてしたのか、フロントガラス側にケツを向けたのかは知る由もないが、案の定、踏まれたせいでボンネットはところどころ凹(へこ)んでいたという。
その人は言った。
「そのころは車にすっごく興味があったから凹まされたのに腹がたって腹がたって……。それにウンコの量だって3人分はあった。いたずらにしては悪質すぎる!」
誰のどのような体調下でのウンコと比較してそれが3人前と言えるのか、私にはよくわからなかったが、もしかすると力士1人の成せるわざということも考えられる。
でもさあ、それって悪質ないたずらじゃないと思うなぁ。
絶対、誰かに恨まれてたんだと思う。
あれ、エリザベートなんて仮名を設定する必要なかったな……
このところ、ウンコだの吐き気だの、美しくない(ということは私らしくない)話のウエートが高くなってしまった。これは当ブログの本流から外れる(とも断定できない)。
オーケストラだったら、若杉弘が言っていたように「マーラーばっかり演ってたら、音が荒れる」状態だ。
よし、爽やかにモーツァルトでも聴こう!
いやっ、だめだ!モーツァルトは糞便愛好家だった!
じゃあ、爽やかじゃあないが、エリザベートのために(やっと仮名を有効利用できた)ブラームスの「悲劇的序曲」を聴こうではないか! ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)は、1880年に「大学祝典序曲(Akademische Fest-Ouverture)」Op.80と「悲劇的序曲(Tragische Ouverture)」Op.81の2つの序曲を書いている。
ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)は、1880年に「大学祝典序曲(Akademische Fest-Ouverture)」Op.80と「悲劇的序曲(Tragische Ouverture)」Op.81の2つの序曲を書いている。
「大学祝典序曲」の方は、1879年にブレスラウ大学の名誉博士号を与えられたその感謝の印にと書かれた。ブラームスはこれを「笑う序曲」と呼んだが、同時にこれと対になる「泣く序曲」も書こうと思い立った。
偉い人の思いつきってよく理解できないなぁ……
「悲劇的序曲」は、しかしながら何らかの具体的な悲劇を頭において作曲されたものではないという。
シューマン(Robert Schumann 1810-56)の未亡人クララ(Clara Schumann 1819-96)に献呈されている。ブラームスは生涯、彼女を愛し続けたというが、かなわぬ愛の悲劇か……って無理にこじつけちゃいけないな。
なお、初演は「大学祝典序曲」よりも先、1880年に行なわれている(「大学祝典序曲」は1881年初演)。
「悲劇的序曲」の演奏では、私はセル/クリーヴランド管弦楽団のものがけっこう気に入っている。そう、村上春樹の「1Q84」の中で、その「シンフォニエッタ」のレコードが取り上げられたおかげで、急に有名になった指揮者セルである(もともとクラシック界では有名だけど)。
セルの演奏は決して感情的にならないのが、かえって悲劇的な雰囲気を醸し出していると思う。1966年録音。
残念なことに現在は廃盤。
エリザベートよ、嘆くなかれ!
きのうはけっこう重度の二日酔いの朝を迎えてしまった。
これまで何度か正直にご報告申し上げているように、近年の私は前の晩に飲みすぎても起床時にはあまり二日酔いの症状がない。あまり食べないで飲むくせがあるので、むしろ飲んだ翌朝は食欲旺盛である。
ところが体調不良は時差をもってそのあとにやってくる。
二日酔いの症状は、まるでチリ沖で起きた大地震による津波が忘れたころに(あるいは能天気に知らないままに)日本に到達するかのように、ずっと経った午前10時あたりに現われるのである。つまり10時のおやつが食べられない。
きのうもそうであった。
起きて、シャワーを浴び、物悲しく小皿に2個のせられ無造作にラップがかけられている、前日の夕飯の残りのコロッケを、ソースたっぷりめで食べた。
ところがきのうの場合、二日酔いの波は、すぐに来た。
ブルドッグ中濃ソースのげっぷ(というよりも“うっぷ”という方がニュアンス的には近い)が、吐き気をもよおしたときに特有の反芻風味を伴って出てきた。
歯を磨いきながら吐きそうになった。清と汚の拮抗状態だ。
はやい、まずい、やばい……
でも、私は出勤するためにいつもの時刻に家を出た。自慢することじゃないけど……
駅に向って歩きながら、何度もツバを吐きたくなる。
梅干を口に入れているわけじゃないのに、泉のようにツバがやけに出てくる。
無味なのはずのツバが、なんとなく苦すっぱい(←造語)味がする。口の中はさわやかの対極の状態にある。
電車に乗ると、車内の中途半端な温もりが優しく吐き気を誘う。
よっぽどカバンに入っているエコバッグを取り出しておこうかと思ったくらいだ。もちろん、いざとなったらそのなかに粗相できるように、だ。
エコバッグは単なる布製だから、その中に吐けば、含水量にもよるが染み出てくるのは間違いない。でも、そのあたりにぶちまけるよりは6億倍ぐらい良い行ないだろう。
それが紳士のマナーというものだ。
ときどきオェッっとくる。いわゆる「からオエッ」である。
私の隣に座った女性は、数分後に立ち上がって別な車両に移っていった。
そりゃそうだ。気づかれないようにいくらさりげなく振舞ったところで、「からオエッ」に気づかないはずがない。そのあとにごまかすためにわざとらしく咳払いをするが、自分でもわざとらしいと本当に思う。もし顔を覗きこまれたら、瞳が苦痛に耐える涙でウルウルしているのがわかるはずだ。朝から涙ぐむサラリーマン……
それに、オエッとならなくても、全身が酒臭いのかもしれない。
一応エチケットのためにガムを噛んでみたが、3回噛んだところで、かえって気持ち悪くなってしまった。たった3回。そのガムは、歯医者で噛み合わせを確かめるゴムの板みたいに歯型の跡が残っていた。
ふう~~~
ため息をつくしかない。
女性が立ち去ったあと、むさ苦しい男子高校生が私の隣に座った。
ふだんだったら、隣に座って欲しくない客層だ。
こいつらは概して清潔感に欠け、インキンの症状軽減を図るためか股を広げ気味に座り、汗臭い。態度も体もでかくて窮屈になる。
でも、彼で良かったとこのときほど思ったことはなかった。
もし私が酒臭かったとしても、彼はそれに気づくほど世間に関心を寄せていないし、ゲームに夢中だったからオエッとなってもならなくてもまったく関係ないのだ。おそらく私が隣でいきなりエコバッグに顔を突っ込んでも、バッグの中にケロッグか何かが山盛りに入っていてそれに食いついていると思う程度だろう。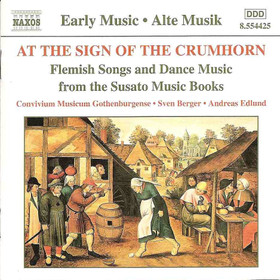 若者ってすばらしい!
若者ってすばらしい!
君の無関心さが嬉しかったぜ!
ナクソスから出ているCDに「スザートの音楽帳/フランドル地方の歌曲と舞曲集」というのがある。演奏はコンヴィヴィヌム・ムジクム・イェーテボリで1997年録音。
スザート(Tielman Susato 1500頃-61頃)はケルン出身で、1543年に楽譜出版社を興し、自作のほか同時代の作品を出版した。
このCDはその楽譜のなかから選曲したものが収められている(のだろう)。
そのなかにソウリィアールト(Carolus Souliaert)という人が作曲した「ほどほどにお飲みなさい(Wilt doch mit maten drincken)」という曲がある。
はい。
すいません……
おっしゃるとおりです……
気をつけます………
先日JRの駅で電車を待っていたら、向かい側のホームを貨物列車が通過していった。
近頃の貨物列車は見ていても全然おもしろくない。
というのも、コンテナばっかりだからだ。
昔は、有蓋車(ゆうがいしゃ)や無蓋車(むがいしゃ)、冷蔵車やホッパー車など実に多彩に飛んでいて楽しかった。最後尾には車掌車もついていたりした。
記号で言えば、ワム、ワキ、トキ、トラ、ホキなどだ。
私は実は鉄道ファンでもあった。
一度、会社の女の子と話している時に、貨車や電車などの記号の意味について不必要にも教えてあげたことがある。
「ワムとかワキなんかの二文字目は積載重量を表しているんだ。ム、ラ、サ、キという4区分がある。最初の文字は貨車の形態とか用途だ。あと、列車のカタカナ記号には、例えば、モハとかキハ、キロ、サハなんかがある」
「へぇ~」
「2文字目は等級で、イ、ロ、ハがある。イは特等車で今はない。ロは一等車で、今ではグリーン車のこと。ハは普通車だ。モというのはモーターを積んでいる車両、サとうのは付随車だ。キはディーゼルカー。だからモハだとしたら、モーターのある普通車。サハならモーターを積んでいない普通車両ということになる。当然、サハのほうが乗っていても静かだ」
「すっご~いっ!」
「そのあとの数字は形式だ。モハ721-025とあれば、721系の25番目に製造された車両。この最初の3ケタの数字が形式を表す。この場合7は交流用。あとの数字は通勤・近郊用なんかの区別でつけられる」
「ふぅ~ん」
そして、数日後、彼女は言った。
「MUUSANって、汽車の記号とか、必要のない知識に詳しいですよね」
「……」
やれやれ。鋭い指摘。
ところで、北海道の人はあまり「電車」と言わない。
というのも、本州に比べ電化が進んでいないからだ。
電化されているのは小樽-札幌-旭川、札幌-室蘭の間だけである。
長距離列車は汽動車、つまりディーゼルカーである。
そのため、「電車」ではなく「汽車」と言う人が多い。
その「汽車」が汽動車の略なのか、機関車から来る「きしゃ」なのかはよくわからないけど……
私はJRについては「列車」と呼ぶようにしている。
会社で「汽車の切符を手配しておいて」というよりも「列車の切符を手配しておいて」の方が、正しいような気がするからだ。
一度、本州の人に札幌から稚内までは1日に何本ぐらい電車があるんですか、と聞かれたことがある。
私は1本もありませんと答えた。
だって、ディーゼルカーしか走ってないから。
正しいことを言ったのに、意地悪と思われなかっただろうか?(もちろんそのあとちゃんと説明したけど)
話を最初に戻すと、そのとき見たコンテナの貨物列車。
その台車となる車両すべてに「突放禁止」と書かれている。
なんとなく意味はわかるが、これってなんて読むのだろう。
「つきはなしきんし」なんだろうか?「とっぽうきんし」なのだろうか?
すっごく気になる……
ところで列車に関する曲を1曲。
ヨハン・シュトラウスⅡ(Johann Strauss Ⅱ 1825-99)のポルカに「観光列車(Vergnugungszug)」Op.281(1864)という楽しい曲があるが、ショスタコーヴィチ(Dmitry Shostakovich 1906-75)がこれを編曲したものが存在する。
私には詳しいことはわからないが、ショスタコーヴィチは1940年にダンス用に編曲したらしい。編曲されたものもオーケストラによるものだが、原曲よりもややテンポが遅く、優雅なものとなっている。なかなか楽しい小曲である。
私が持っているCDは2枚組のショスタコーヴィチ管弦楽作品集だが、現在は入手困難。
もともとのJ.シュトラウスの曲も名曲だが、さすがショスタコーヴィチ、原曲の質を落とすことなくあらたな響きを生み出している(かなりひいきしちゃってるかな?私の場合、マーラーやショスタコの曲にはやや泥酔、いや心酔気味なので割り引いてくださっていいです)。
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
- 12音音楽
- J.S.バッハ
- JR・鉄道
- お出かけ・旅行
- オルガン曲
- ガーデニング
- クラシック音楽
- コンビニ弁当・実用系弁当
- サボテン・多肉植物・観葉植物
- シュニトケ
- ショスタコーヴィチ
- スパムメール
- タウンウォッチ
- チェンバロ曲
- チャイコフスキー
- ノスタルジー
- バラ
- バルトーク
- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽
- バロック
- パソコン・インターネット
- ピアノ協奏作品
- ピアノ曲
- ブラームス
- プロコフィエフ
- ベルリオーズ
- マスコミ・メディア
- マーラー
- モーツァルト
- ラーメン
- ルネサンス音楽
- ロマン派・ロマン主義
- ヴァイオリン作品
- 三浦綾子
- 世の中の出来事
- 交響詩
- 伊福部昭
- 健康・医療・病気
- 公共交通
- 出張・旅行・お出かけ
- 北海道
- 北海道新聞
- 印象主義
- 原始主義
- 古典派・古典主義
- 合唱曲
- 吉松隆
- 名古屋・東海・中部
- 吹奏楽
- 周りの人々
- 国民楽派・民族主義
- 変奏曲
- 多様式主義
- 大阪・関西
- 宗教音楽
- 宣伝・広告
- 室内楽曲
- 害虫・害獣
- 家電製品
- 広告・宣伝
- 弦楽合奏曲
- 手料理
- 料理・飲食・食材・惣菜
- 映画音楽
- 暮しの情景(日常)
- 本・雑誌
- 札幌
- 札幌交響楽団
- 村上春樹
- 歌劇・楽劇
- 歌曲
- 民謡・伝承曲
- 江別
- 浅田次郎
- 演奏会用序曲
- 特撮映画音楽
- 現代音楽・前衛音楽
- 空虚記事(実質休載)
- 組曲
- 編曲作品
- 美しくない日本
- 舞踏音楽(ワルツ他)
- 行進曲
- 西欧派・折衷派
- 読後充実度
- 邦人作品
- 音楽作品整理番号
- 音楽史
- 駅弁・空弁
© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」

