あなたは救急車に乗ったことがあるだろうか?
ファルケはある。
私もある。
ファルケのことは忘れるとして、私の場合は5年前。
大阪で単身赴任生活をしていたときだった。
明日からお盆期間に入るという日の夜中。
ひどい寝汗をかいていた。シャツがびちゃびちゃに湿っていた。暑いのではない。寒気がする。真夏だというのに布団をかける。
すると、ますます汗をかく。寒気がするけど、暑いのだ。まるで、足の裏が痒いのに、掻くとくすぐったいのと同じジレンマだ。
しかも左足が痛い。膝の裏の部分だ。何だか寝苦しくて水を飲みに行く。足に激痛が走る(話の展開を先取りすると、つまりこのときはまだ歩けたのだ)。その痛みによって、全身に震えが走る。再び寝る。何度も目を覚まし、朝になる。
仰向け状態のまま起き上がれない。左足の膝の裏が痛くて足が曲げられない。伸ばせもしない。じゃあどういう状態なのかというと、中途半端な状態だ。膝自体は腫れたりしてもなく、外観はいつもと同じ。まばゆいほど美しい。
体勢を横向きにする。左に向こうとしても右に向こうとしても、激痛が走りうまくできない。このとき巨大なゴキブリが私に近づいて来たなら、超人的気力で飛び起きたのだろうが、この部屋の中では、私以外すべて平穏に時が流れている。顔の上にある蛍光灯のナツメ球のボーっとした明かりが自分の惨めな気持ちに拍車をかける。
もし、蛍光灯が天井からはずれて落下してきたら、わたしは下敷きになって弱り目にたたり目状態になっただろう。
試行錯誤の上、何とか部屋のドアに近づけた。ノブに手を伸ばし、しっかりとつかんで、ノブを支えにしてゆっくりと立ち上がる。ここでノブが折れたり、ドアが外れたら、再び一からやり直しだ。慎重に作業を進めた結果、やっと立てた。
こんなにゆっくり歩いたことがあっただろうかと思うくらいの速度で歩く。分速1m位だ。この部屋に蟻がいたら、私はたやすく追い抜かれただろう。歩くたびに左膝(の裏)に激痛が走る。まるでHなことを考えている不良少年のように息遣いが荒くなる(Hなことを考えていたのではなく、痛いから息遣いが荒くなったことを申し添えておく)。
何とかキッチンまでたどり着く。が、キッチンに用事がなかったことに気づく。しょうがないから流し台の前でタバコを吸う。こういう状況でもタバコは吸いたくなるものなのか?その習慣性に驚く。
とにかく痛い。単なる寝違えだろうか?でも、膝の寝違えなんてあまり聞いたこともないし…。まるで、朝青龍に足を180度ひねられたような痛みだ。
だが、起きた時は立ち上がれもしなかったのに、今は生後1ヶ月の赤ん坊よりは歩けるようになっている。確実に状況は良くなってきているのだ。もう少し時間が経てば跳びはねられるようになるかも知れない。
とりあえず会社の同僚に電話をする。
この人物は男だが、顔以外は全体的傾向として女性っぽい。
呼び出し音、トゥルルルルル×8回。早く出ろよ!
「おはようございまぁ~す」
相変わらず大きいのに能天気な声だ。
「足が痛くて歩くのがやっとだから、這って行く。だから今日中には事務所に着かないかも知れない。場合によっては美容院に行って髪を結ってくるかも知れない」
「きゃあぁぁぁぁ!どうしたんですかぁ?」
「わからない。こっちが教えてもらいたいくらいだ」
「心配ですぅ~。お大事にぃ~」
本当に心配してるのか?
次に札幌にいる妻に電話をかける。
「なぜかわからないが、足が痛い。やっと立ち上がったところだ。様子をみてみるが、病院に行くかも知れない」
「不摂生のせいじゃないの?痛いってどういう風に痛いっていうの?ビールの飲みすぎじゃないの?…」
「耳も痛くなってきたから切る。どうするか決めたらまた電話する」
私がこんなに苦しんでいるというのに、なぜ説教されなきゃならないんだ。お前は坊さんか?
そういえば、立ち上がってからというもの、ずっと立ったままだ。膝が曲がらないので座れないのだ。かといって、まかり間違って横になったら、起き上がるまで再び多大な労力と時間を要する。いや、二度と二歩足で立つことは無理かも知れない。クララの気持ちがよくわかる。もし、ここにハイジがいて「意気地なし!立ってごらん!」と言われたら、私は大泣きする以外なかった違いない。
でも、座りたいという欲望を捨てきれない。
人間、いつだって好奇心と冒険心と探究心は大切なのだ。
私は左足を伸ばしたまま、スローモーションのようにテーブル(ちゃぶ台)に腰を下ろした。腰を下ろす間、時折左ひざに激痛が走る。「痛っ!」。私の叫びが部屋の中に空虚に響く。でも、痛いときに時々笑いたくなるのはなぜだろう。
やっと座った。が、座ってもすることがないことに気づく。立ち上がろうとする。立ち上がれない。それでも5分くらいかけて、何とか立ち上がる。ここでテーブルの脚が折れたりしたら、私は絶望的なダメージを受けたに違いない。
再びゆっくりとキッチンへ向かう。電池が切れる寸前のゴジラ人形のような歩みだ。
そんなとき、今朝は珍しくタイマーをセットしてご飯を炊いたことを思い出す。とても食べる気にはなれない。が、放っておけないので、炊飯ジャーを開け、茶碗1杯分くらいずつ小分けしラップで包む。
突然3m先のテーブル(先ほど意味もなく座ったところだ)に置いてある携帯電話が鳴る。妻からだ(妻からだということは、着信履歴であとで知った)。そちらに向かって足を踏み出すが、たどりつくはるか前に切れる(テーブルにたどり着くのに数分かかったのだ)。
重い気持ちでこちらからかける。
「すまない。電話にたどり着くのに時間がかかったんだ」
「で、どうすることにしたの?」
「まだ決めてない」
「まだ決めてないって、どういうつもり?」
「どういうつもりもない。病院に行こうと思う。また、連絡する」
頭痛までしてきたような気がした。
とはいえ、どこに病院があるのかわからないし(私は大阪に来てから、この地で病院にかかったことがなかった)、この足ではどこにも行けない。
そこで私は救急車を呼ぶことを決意した。
しかし、こんなに汗をかいてしまった。これでは恥ずかしくて人に会えない。汗を流したい。それに、風呂で足を温めれば症状が良くなるかもしれない。
浴槽にお湯をためる。
パジャマを脱ぐ。足が曲がらないので、パジャマのズボンを脱ぐのも大変だ。パンツも脱ぐ。足が痛いのでパンツを脱ぐのも大変だ。ここで大地震がきたら、スッポンポンの格好のまま逃げ遅れてしまうだろう。
お湯がたまった。
浴室に入ろうとする。その段差を乗りこえるのに一苦労だ。バリアフリー住宅の必要性を強く感じる。浴室に入る。ここで足を滑らせたらとんでもない格好のまま動けなくなるだろう。そう思うと、一人で宇宙遊泳に行くような緊張感がみなぎる。
そして……ここになってようやく、こんな足で浴槽に入ることなど到底不可能であることに気づく。またげないのだ。
万が一入れたとしても、足が曲がらないのに、肩までつかって100数えることなんかできない。百歩譲って、肩までつかったとしても、再び立ち上がれる保証はまったくない。もし、立ち上がれなかったら、冷えていくお湯の中で、そのまま素っ裸で震えながら身動きできなくなる。栓を抜けば水の中に居続けなければならないことは回避できるが、素っ裸で身動きできないことには変わりない。
賢明なる私はこのような自殺行為を避け、シャワーを浴びる。膝が曲がらないので、浴室から出るときも、体を拭く時もたいへん不自由だ。出来損ないのロボットのようだ。
ふつうのズボンは吐けないので、短パンタイプのズボンを履く。
「救急車を呼ぶことにした」と妻に連絡を入れ、119番をダイヤルする。
「火事ですか?救急ですか?」
「膝です。いえ、救急です」
住所と名前を伝え、鍵を開けて、お迎えを待つ。長く感じたが5分くらいで来たのだろう。
簡易担架で1階まで運ばれる。そのあと、歩道上で、簡易担架ごと担架に移される。
通行人は誰も見向きもしない。恥ずかしい思いをしなくてすんだ。都会の無関心さに感謝だ。
救急車のなかで、1人は電話で受け入れてくれる病院を当たっている。残り2人は何度か名前や住所、電話番号、生年月日を尋ねる。どうやら、意識がはっきりしているかどうか確認しているのだ。ここで、住民票の写しの提出を求められたら危うかった。私がここの市民でない、つまり住民税を納めてないことがばれてしまう。そういう場合は、料金メーターを取り出してくるに違いない。
血圧を測られ、聴診器を当てられる。どちらも正常と言われ、膝の痛みで呼んだくせに、なぜか他は健康なことにほっとする。搬入病院が決まり、救急車は5分くらいのところにある病院に走った。が、どこをどう走っているのか見当がつかない。もし、乗り物に酔いやすい人なら確実に吐くと思われるほど、乗り心地はよくない。
病院に着き、仰向けに寝たまま、医者が来るまで随分長く待たされた。医者が来て膝を触られると飛び上がるほど痛い。実際に飛び上がらなかったのが不思議なくらいだ。背筋(はいきん)が弱くて何よりだと思った。膝に注射針を刺される。水を抜くという。この注射がまたひどく痛い。が、結局、水はほとんどたまっていなかった。
痛み止めの座薬を入れられる。「自分で入れます」と看護婦に入れられるのを固辞しようとしたが、されるがままに入れられる。採血され、その結果がでるまでの間、別な部屋で寝て待つ。
その部屋のベッドに移るのがまたたいへんだった。足がジンジンと痛む。痛み止めの薬が効いてくる様子はない。
1時間ほどして医者が来て、血液検査もなんともないという。帰ることとするが、やはり立ち上がるのもやっとだ。医者は「何なら入院していってもいいよ」という。医者が良く使う手段だ。これで同意したら、数十日も出られなくなる可能性がある。私は、明日から北海道に出張しなければならないと答え、お泊りを拒否する。
すると、体格のいい看護婦が松葉杖を持ってきた。私がそれを使わずに立とうとすると、その看護婦は足の先を洗濯バサミで挟まれたタコのような、驚いた顔をした。
「何するの?」
「いえ、何とか自分で立てないかなと思って」
看護婦はアメリカ人のような大げさなジェスチャーで、「ダメ、ダメ、ダメ」という風に手を振った。
自己流で松葉杖を使って会計に向かおうとすると、別な看護婦らしき人が来て、別室に案内された。リハビリテーション科と書かれたその部屋で、望んでもいないのに、松葉杖の正しい使い方のレッスンを受けた。
やっと終わり会計を済ませ、タクシーで帰る。タクシーの乗り降りも痛みでままならないが、松葉杖をついているせいか、運転手は妙に親切だ。そして、この病院がどのあたりにあったのか初めて知り、住んでいるマンションに意外と近いことがわかった。
そんななか、あの同僚からメールが入る。
午後に2つの打合せを入れやがった!まったく状況を把握できないヤツだ。
が、家に帰って少し時間が経つと痛みが和らいだ。会社に向かうときには、松葉杖をつかなくても、自力で何とか歩けるようになった。薬が効いたのか、時間とともに快方に向かったのかわからないが、とにかく私の救急車初体験の1日は終わった。
119番。 バルトーク(Bartok,Bela 1881-1945 ハンガリー)のピアノ協奏曲第3番SZ.119(1945)。
バルトーク(Bartok,Bela 1881-1945 ハンガリー)のピアノ協奏曲第3番SZ.119(1945)。
Sz.はスールーシ(A.Szollosy)による作品目録(1956出版/1965改訂)の番号である。
この曲は未完の作だが、バルトークが亡くなったときにはほぼスコアは完成しており、略語で書き残された最後の17小節を、弟子のT.セアリーが完成した。
バルトークの作品の中でも人気が高い曲で、始まり方や終わり方なんかちょっと近未来的。第2楽章は童謡の「ぴっちぴっち、ちゃっぷちゃっぷ、ランランラン」を思い出させるようなメロディーもある。
バルトークは死の床で、「まだ表現すべきものが非常にたくさんあるのに、この世を去らねばならないのが残念だ」と語ったという。
CDはラッセル・シャーマンの独奏、ギーレン指揮南西ドイツ放送響のものを。
1989年録音。アルテノヴァ・クラシックス。
ほかに「2つの肖像」と「弦チェレ」が収録されている。
ここに載せたCDジャケットは旧盤のもの。
救急車まで呼んだ私の“痛み”のその後の話については、いずれまた……
January 2010
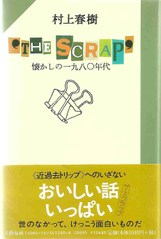 村上春樹の「THE SCRAP」(文芸春秋社)のなかで、ベートーヴェンのピアノ協奏曲(というよりもレオン・フライシャーというピアニスト)について書いてある文がある。
村上春樹の「THE SCRAP」(文芸春秋社)のなかで、ベートーヴェンのピアノ協奏曲(というよりもレオン・フライシャーというピアニスト)について書いてある文がある。
そこで私の記憶もよみがえる。
私が通った高校は、札幌市東区にあるK高校だが、良く言えば自由な校風、悪く言えばしまりのない雰囲気の学校だった。
入学式。
「新入生入場」とアナウンスがあり、体育館に「ジャーン」って、ベートーヴェンの「皇帝」が流れる。かわいい新入生が入場してくると、私たち在校生はトイレットペーパーを紙テープの代わりにみたて、彼ら彼女らに放り投げて歓迎するのである(私はこの犯罪行為に直接関わったことはない)。それにしても、トイレットペーパーが一般的でなかった時代には、“茶チリ”でも舞っていたのだろうか?
ということは、私が新入生で体育館へ入場したときも、この曲が流れていたのだろう。しかしまったく記憶にない(耳が緊張していたのかもしれない)。
でも記録によると、私がこの作品を初めて聴いたのはその年の夏だったので、自分の入学式のときにはそこに流れている曲が果たして何であるかは認知してなかったということになる。
あぁ、いま明かされる真実。なんだか、本当に自分があの高校に入学したのかどうかの自信すらなくなってきた…
私にとっては、初鑑賞以降、何度聴いても「皇帝」は長ったらしくて退屈な音楽の仲間に分類されていた。モーツァルトのピアノ協奏曲群も退屈だったけど30分以上かかる曲はあまりないからまだ耐えられた(いや、ウソだ。コンサートでも何度か眠ってしまった)。
しかし「皇帝」は長い。それまで書かれていた協奏曲と違い、40分程度を要する。しかも第1楽章が曲の半分近くを占める。
この曲を初めて生で聴いたのは、大学受験を数ヵ月後に控えた78年11月だった。その演奏会もひどく退屈だった。長時間の着席のために、お尻が石灰化現象を起こすのではないかと思ったくらいだ。
聖書の中に、ソドムが神に滅ぼされるときに、ロトの家族は救われるが、神の言葉に従えなかったロトの妻は塩の柱になってしまったという話がある。死海の近くに「ロトの妻」と言われる岩塩の柱があるそうだ。
このときの私も、頭は「塩の頭(かしら)」になっていたような気がする。だって、しょっぱかったもん、切れた唇の血が。
しかし、第3楽章が始まったときには胸が躍った。「あぁ、やっと最後の楽章になった。もう少しの辛抱だ」と。
しかしこの日の演奏会は、私にはちょっぴり記念碑的なものだった。精神的な病からの復帰記念演奏会だったのだ(あたかも自分が演奏者のような言い方だが)。
私はこの日、ほぼ1年ぶりに演奏会を聴きに出かけたのだった。
私は中学のときから札幌交響楽団の定期会員になっており、毎月の定期演奏会を聴きに行っていた。しかし、高校2年の12月に行った演奏会を最後に、会員は続けていたものの会場にはずっと行っていなかった。チケットはすべて捨てていたのだ。
なぜか?
恋よ!恋のせいなのよ!
恋はすべてを美しくする。のではなく、私の場合は無気力にする。演奏会に行くのも億劫になった。なぜ人を好きになったことで、月1回の演奏会に行くのも億劫になったのか?それはうまく説明できない。自分でも理由が分からないからだ。演奏会に行くのは億劫じゃないが、学校に行くのは億劫だということにならなくて、これ幸いであった。
しかし私は自分の気持ちを彼女に伝え、粉砕した。まさに粉砕だ(この相手は幻想交響曲の記事のときに書いた女性だ)。
私の気持ちは、まずは斧で大まかに割られ、次に鉈(なた)で扱いやすいように細かくされ、さらにオルファ・カッターで削ぎ(そぎ)切りされ、削り節のようになった断片はすり鉢に入れられ、スリコギで粉状にされ、折からの強風で空(くう)に飛び散ったのだった。
そのあとの私の気持ちは、あたかも人類が滅亡した日の翌朝の空のように晴れわたっていた。
「女なんてなんだ!私は女嫌いになる!よし、また音楽を聴こう!音楽は私を裏切らないのだ!気が向けば修道院にも入ろう。禁欲は美徳だ」
その後も気が向かなかったのは何よりであったが、そのように悟りを開いたあとの最初の演奏会が、この日だったのである。演目に「愛の喜び」とか「愛の挨拶」「昭和枯れススキ」などが入ってなくてよかった。
ピアノ独奏はまだ若かりしエリック・ハイドシェック。指揮は大町陽一郎(最近、この指揮者の動向についてさっぱり耳にも目にもしない)。
このような状況下で、私はベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)のピアノ協奏曲第5番変ホ長調Op.73「皇帝(独:Kaiser,英:Emperor)」(1809)の生演奏を聴いたのだった。
先に書いたように、このときの演奏の印象は、お尻だけが覚えている。頭には演奏そのものの記憶はない(だって「塩の頭」になっていたから)。が、ステージ上で印象的だったことがある。曲が終わり、聴衆の熱烈なカーテンコールで何回も舞台と袖の間を行き来していたハイドシェックが、最後に困ったような顔をして自分の腕時計を指差し、「アーメン、ラーメン、チャーシューメン。グーグーナルヨ、ハラドケイ」みたいなことをしゃべったことだ。
どうやら、その晩のうちに東京に行かねばならず、「汝たちのわが演奏に対する熱烈な拍手はありがたいことなれど、われ、今宵、飛行機に乗らなければならぬ。さらばじゃ」と言ったらしい。こんな珍しい光景が見られたのである。別に楽しい光景ではないが…
ちなみに、このあとの演目はブラームスの第4交響曲。しっとりした悲しげな曲だ。私は聴き通す自信がなくて、「皇帝」だけ聴いて帰った。涙を流してしまう恐れがあるからではない。私の赤ちゃんの頬のような柔らかな桃尻が、内出血でブス色になってしまうのを避けるためだ。
「皇帝」については、もう一つ思い出がある。テレビで放送されたのを観たのだが、「コンペティション」という映画に関してのことである。
この映画、その題名どおり競争なのだが、それはピアノ・コンクールの話。何度もコンクールに出ては優勝できずにいる主人公の男が、これが最後の挑戦ということで参加するのだが、彼が弾く自由曲が「皇帝」。
一方、ライバルであり―映画のワンパターン的展開であるが―恋に落ちる相手(この場合、あくまでノーマルに女性である)の自由曲がプロコフィエフのピアノ協奏曲第3番(最終戦でアクシデントがありモーツァルトから急遽プロコに変更)。
私なんざ、この選曲でもう女性の勝ちだと思った。だって「皇帝」は退屈だもの。プロコの方はカスタネットまで入って楽しいわ。そして映画の結末は、私の読みどおりこの女性が優勝。
しかし、しかしである。私もそこそこ年齢を重ねるごとに、この「皇帝」が名曲と言われる意味が解ってきたような気がしたことも多少なりともあるような日々を送るようになった気がしないでもなくなった。やっぱり名曲だ、この曲。
協奏曲という作品形式を飛躍的に発展させた(とか何とか)いう音楽史的な重要性もさることながら、耳にしていて感動するようになった。
だから、そこの若者よ。いま良い曲だと感じなくても結構。もしかすると、あと何年か、何日か、何秒かしたら、ふと感動のため息を漏らすかも知れないのだ。あせることはない
ところで、考えてみれば、私にとってベートーヴェンとはどういう位置付けにある作曲家なのだろう?「そんなこと聞かれても知らないですわ」と言われるのがオチだろう。独り言なのだから放っておいてほしい。
ところで、なぜベートーヴェンは偉大なのか?
《ベートーヴェンと彼以前のすべての音楽家を隔てる差異は、ベートーヴェンが自分自身を芸術家とみなし、芸術家としての自分の権利を正面から主張したことであった。モーツァルトが貴族世界の周辺を動き、ドアを一心に叩いても本当の意味で中に入れてもらえなかったのに対し、モーツァルトより14歳しか年少でなかったベートーヴェンは、ドアを蹴り飛ばして押し入り、自分の住み家にした。自分は芸術家で創造者であり、したがって王侯貴族より優れている、というのであった》(H.C.ショーンバーク「大作曲家の生涯」:共同通信社)
ベートーヴェンは、一般的には「天才」ということで(あるいは聴覚を失ったにもかかわらず作曲をし続けたということで)「大作曲家」と位置付けられているが、ここに書かれていること、つまり歴史上初めて「自らを『芸術家』とみなした」ことが、この音楽家の最大の特徴である。
彼は「あなたが侯爵であるのは、生まれから来た偶然に過ぎません。それに引きかえ、私は自分で自分の世界を築きました。侯爵は何千人もいますが、ベートーヴェンはただ一人です」とまで言っているのだ。
確かに彼には比類なき「力」がある。それは彼の音楽を聴けばわかる。と同時に、彼の音楽はとてもロマンティックでもある。
ピアノ協奏曲第5番は、彼の5曲あるピアノ協奏曲の中で最大規模の作品。彼はその前の第4番の協奏曲で、曲の開始を独奏ピアノから行なうという、これまでにない手法を使ったが、この作品でもオーケストラの一撃のあと、すぐさまピアノがカデンツァ風に堂々と演奏され (冒頭部分のスコアを掲載しておく。このスコアは全音楽譜出版社のもの)、そのあとにオーケストラが第1主題を提示する。
(冒頭部分のスコアを掲載しておく。このスコアは全音楽譜出版社のもの)、そのあとにオーケストラが第1主題を提示する。
ピアノのソロは、過去のピアノ協奏曲にみられないほど技巧的。その一方で、それまでは演奏者の即興に任せられていたカデンツァは、ベートーヴェンが短い独奏を指示している。
第2楽章は瞑想的な主題に基づくロマンティックな変奏曲、第3楽章は力強いロンドである。第2楽章と第3楽章は続けて演奏されるが、その部分でピアノのバックで吹かれるホルンの長い持続音は、ホルン奏者泣かせの箇所である(息が続かない)。
なお、「皇帝」の名称は、作品のもつ堂々とした感じや華麗さから、誰言うともなくついたもの。私には「奔放な貴婦人」のように聴こえるけど……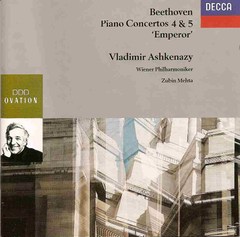 私が長年愛聴している演奏は、アシュケナージの独奏、メータ指揮ウィーン・フィルのもの。
私が長年愛聴している演奏は、アシュケナージの独奏、メータ指揮ウィーン・フィルのもの。
1983年の録音。デッカ。
さてと、今日明日は出張。
「皇帝」を聴きながら、高低差のある旅をしてきます(飛行機に乗るってこと)。
「ワタシはァ、チューダー朝のォ、偉大なる作曲家のォ、末裔なるぞよ」と、聞く人が聞いたら「うさんくせえヤツだ。だいたいこの顔、信用できるのか」、と誤解を招きかねないようなことを言っている作曲家(誤解じゃないかもしれないけど)。それがジョン・タヴナー(John Tavener 1944- イギリス)である。
タヴナー(タヴァナー)は、前衛音楽の崩壊後に活躍している神秘主義の作曲家。
自分は、16世紀イギリスの代表的教会音楽家J.タヴァナー(John Taverner 1495以前-1545)の子孫であると称している。
それがホントかウソかは知らないが、“自称”というのが何とも怪しい。
“癒しの音楽”を書いているが、宗教的には正教徒からイスラム教へ改宗したとも言われており、このあたりも本当に癒されるのだろうかと、信じきれない不安がある。
1968年作曲のカンタータ「鯨」でレコード・デビューしたとき、そのレーベルがビートルズのレコードでおなじみ(というには時が経ちすぎているけど)のアップル・レコードからだったというのも、クラシック音楽界としては異端。
なんとなくヴェールに包まれた人物だ。どうせだったら顔もヴェールで包んだままにしておけばよかったのに……
そのタヴナーの「聖母マリアの御加護のヴェール(奇蹟のヴェール)(The protecting veil)」(1987)。 「奇蹟のヴェール」は、チェリストのスティーヴン・イッサーリスのプロミス・デビューのために書かれた7つの楽章からなるチェロとオーケストラのための作品。
「奇蹟のヴェール」は、チェリストのスティーヴン・イッサーリスのプロミス・デビューのために書かれた7つの楽章からなるチェロとオーケストラのための作品。
むかぁし、昔、10世紀のこと。
東ローマ帝国のキリスト教の大都市コンスタンティノポリス(コンスタンティノーブル。現イスタンブル)にイスラム教徒が侵入しようとしたとき、キリスト教徒を守ったとされるのが“奇蹟のヴェール”。どんな光景か想像できないが、とにかくそれをテーマにしている曲だ。
この曲、イギリスでは大ヒットしたらしい(そういえばグレツキの交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」も、ロイド=ウェッバーのレクイエムも、イギリスで大ヒットしたという。こういうのが好きなのかな、えげれすの人は)
各楽章のタイトルは、
1. セクションⅠ
2. 受胎告知
3. 顕現
4. 架刑と聖母の悲しみ
5. キリストは甦った
6. 聖母の死
7. 奇蹟のヴェール
である(下のCDの表記による)。
冒頭からどこまでも美しい。
どこまでも美しいという言葉はヘンだが、どこまでも美しいのだ。
わかりやすく変換するなら、とても美しい、ってことだ。
癒されたいときにはもってこい。
私はいつも癒されたいと思っているが(ナマケからではなく、傷つきやすいからだ)、こればかり聴いているとぬるま湯から脱出できなくなりそう。だから私は、マーラーやらショスタコーヴィチやら、時にはジョン・ケージなんかを聴いて刺激を受けることを辞さないようにしている。
それはけっこうな冗談としても、ホント、きれいな曲。
ちょっぴりカーニスの音楽を思い出しちゃった。
そして、4日前、私はカニ酢を食べちゃった(これホントの話)。
CDはナクソス盤を。
マリア・クリーゲルのチェロ、湯浅卓雄指揮アルスター管弦楽団。1998年の録音で、規格番号は8.554388。カップリングはソプラノ、テープとオーケストラのための「イン・アリウム」。
先日北海道新聞に載った演劇(?)の広告を何気なく見ていたら、懐かしい漢字の配列を発見した。
“伊藤珠貴”という名前である。
この催し物(演劇?)は今年の3月に札幌で行なわれる「春の夜想曲~菖蒲池の団欒」というもの。
菖蒲池での団欒といえば、数年前の夏に明治神宮の菖蒲咲く池で重なり合ってうごめいていたカメさんたちを私は思い出してしまったが、これはカメの世界とは関係ないだろう。間違いなく。
これで音楽を担当するのが土田英順さんと伊藤珠貴さんと書かれている。
土田氏は元札響の主席チェロ奏者。
伊藤氏は、その後ネットで調べたら、札幌で活躍するピアニストということだ。
この伊藤珠貴という同じ名前の女の子、小学校(もちろん札幌)のときの同じクラスにいたのだ。
その子はピアノを習っていた。
しかも巧かった。
中学に進んでからは同じクラスになったことはなかったが、ピアノはさらに巧くなったはずだ。学校行事のときの合唱の伴奏などをやっていた。
こう考えると小学生のときに同級生だった伊藤珠貴ちゃんは、現在札幌で活躍しているというピアニストの伊藤珠貴さんと同一人物である可能性が高いと言わざるを得ない。もしそうだったら「わたしゃ音楽家、山のタマキィ~」なんて歌って悪かった(でも、私は主犯格じゃなかった)。
実は伊藤さんは、過去に「チョピン,ショピン,ショパン」という記事の中でで登場している。この記事の主人公だった又靄さんではない。貴藤さんという偽名、いや仮名で登場していただいている。そのときは何にも考えないで書いたけど、その後もピアノ人生をおくっていたとは、ある種、驚きもある。
ここまで書いたのに、実は同姓同名の別人だったらやれやれだけど。
でも、当たり前のことなのかも知れないが、小学生のころ彼女がどんな曲を弾いていたのかまったく覚えていない。あるいは耳にする機会がなかったのかもしれない。そのころは私もクラシック音楽に傾いていなかったことだし。
一度彼女の家に友人と遊びに行ったことがある。
昼になり、彼女のお母さんがインスタントラーメンを作って出してくれた。
そこには大きめのピーマンが入っていた。
ピーマンはあまり得意でなかったが、私はそれを食べることができた。
些細なことだが、ピーマンを食べられるようになったのは彼女のお母さんのおかげである。インスタントラーメンにピーマンというのは冷静に考えれば珍しいトッピングだけど。
ところで中学2年のときだと思うが、つまり私がクラシックを聴くようになってからだが、なぜか彼女が出たピアノ発表会を聴きにいったことがある。たぶん、彼女が通っていたピアノ教室の発表会だと思う。というのも、他に知っている子が何人か出ていたからである。
しかし伊藤さんの演奏は何一つ記憶に残っていない。
そもそも本当に出ていたのだろうか……
唯一記憶にあるのは1学年下の、顔だけは知っていた頑丈な体つきの女の子の演奏だ。曲はベートーヴェンの「悲愴」の終楽章。
当時の私はこの曲を知らなかったのだが、大きな体を揺さぶり大きな手で力強く弾く姿に、そら恐ろしいものを感じた。悲愴なピアノ。
なるほど、ピアノという楽器は「頑丈である」ことも重要な要素であると思ったものだ(椅子はさらに丈夫さを求められるだろう)。
彼女は途中、楽譜を2枚めくってしまい、2ページ分ショート・カットしてそのまま引き続けたそうだ。そんな話あるんかい!(私がこの話をどこで聞いたのかも覚えていないが)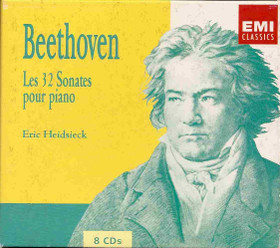 ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)のピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」Op.13(Sonate fur Klavier No.8 “Pathetique")。1797年頃から98年にかけて作曲されたもので、ベートーヴェンの初期ピアノ・ソナタとしては最も劇的な作品である。
ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827 ドイツ)のピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」Op.13(Sonate fur Klavier No.8 “Pathetique")。1797年頃から98年にかけて作曲されたもので、ベートーヴェンの初期ピアノ・ソナタとしては最も劇的な作品である。
「悲愴」というタイトルはベートーヴェン自身が付けた。
ショート・カットしたその子は、でも堂々としてステージを去った。
もしかしたら飛ばしたことに気づいてなかったのか?
「悲愴」は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタのなかでも、第14番「月光」、第23番「熱情」とともに3大ソナタとも言われる名曲。
CDは以前にも紹介したハイドシェックによる全集盤を私は聴いている。
ひどい朝だった。
昨日の朝のことだ。
いや、私の朝はほとんどひどいものなのだが(でも、喜びに満ち溢れて目覚める人っているのだろうか?)、昨日は特にひどかった。
ひゅるるるという音(車のファンベルトが緩んだのではない)
吹雪だ。
清水脩の合唱組曲「山に祈る」の中で、吹雪はアルピニストの前に立ちはだかる、といったようなセリフが語られる。
私はアルピニストでもピアニストでもアルビノーニでもないのに、これから吹雪に意地悪されるのは明白だ。ずる休みしない限りは。
しかしながらテレビのお天気情報では、いま都心部では雪がやんでますと、あまり悲劇的ではないことが語られている。
札幌の西半分は、手稲山が日本海からの風雪を妨害してあまり降ってないらしい。
だが、わが陣営、東半分は吹雪である。
こういうときだけ手稲山が来てくれたら助かるのに。
しかも今回の吹雪は、私の優雅な出勤時間(孤独になれる貴重な時間だ)を直撃。
さあ、いざ出陣(出勤)!
ウォークマンのイヤホン(という言葉は古い!ラジオで競馬中継を聞いてるようなイメージがある。インナーイヤーヘッドフォンというらしいが、耳の中に突っ込むヘッドフォンというのも実に奇妙な言葉だ)を耳に突っ込み、耳あてをし、フードをかぶる。
こうやってあらためて書いてみると、耳だけは完璧だ(他は完璧でない)。
幹線道路に出るまでの道の歩道は、過去の除雪によって雪山と化しており使えない。
こんなときに馬鹿正直に「交通ルールを守ろう。歩道を歩こう」なんて正義感を起こしたら、腰までぬかって身動きできなくなる。
だから車道の、車が通った跡、雪が踏みつけられたわだちを、平均台競技が苦手なやじろべえのようによろよろと歩く。それでも雪が靴に入り込んでくる。入り込んだ雪は楽しそうにすぐに水に変身する。こういうとき長靴で出勤できたらなんて幸せだろうか、と思う。
イヤーン・イヤーンじゃなくて、インナーイヤーなんとかのおかげで周りの音が聞こえないから、ときどき振り返って、車が私を轢こうと迫って来ていないか確かめる。それだったら音楽を聴かなければいいだろうと思うだろうが、いずれ電気自動車時代が到来したら、どっちにしろ同じような行為を強いられるだろうから、今からその練習である。
その結果、電気自動車を普及させるためには、冬場でも安心して歩ける常夏状態の歩道の確保が不可欠という結論を、この吹雪の中で思いついた。
それにしても、電気自動車は静か過ぎて接近したのがわからず危険だから、音を出すようにしろ、という発想はわからんでもないが、何かおかしいと思う。静かで環境に優しい車を開発したのに、文句をつけられている自動車メーカーがかわいそうだ。職場で黙々と事務仕事をしていたら、積極性が足りないと嫌味を言われてるようなもんだ。
だったら、電気自動車を所有・運転できる資格として、例えば、右翼団体の街宣車に改造し、走行中は絶えず伝統的な日本音楽を周囲に気づかれるように流すこと、なんていう条件設定をしなくてはならないだろう。
幹線道路に出る。
幹線道路といっても、もはや血栓だらけの血管のようになっている。雪の色というものが真紅でなくてよかった。
ある程度覚悟していたが、歩道はまったく除雪されていない。
もう少しあとになったら小学生の通学のために除雪が入るのだが、いまはまだ7時。自然のなすがままの状態である。
すでに先駆者が残していった足跡をたどって前に進もうとするが(どうやら今朝ここを歩むのは、私が2人目らしい)、この見知らぬ先駆者、妙に歩幅が広い。雪男じゃないかと思ったくらいだ。ウーっ!(←わかる人はわかる)
しかも幹線道路に入ったとたん、完璧な向かい風。
顔面をピシピシと雪が直撃。かわいい頬が痛い。
ズボンを履き忘れてきたんじゃないかってくらい、下半身がスースー、冷え冷えする。
メガネの表面にどんどん雪が付着する。しかも回り込んだ雪がレンズの裏側、つまり眼球側にまで付着する。水中メガネがあったら便利だなと思う(このときはゴーグルという発想には至らなかった。ふだんグーグルを利用しているのになぜ気づかなかったのだろう?)。
カバンにも雪が付着。
このとき痛感したのは、カバンの外側にファスナーで閉じられないポケットはないほうがいいということ。雪が入り込んで、たまり、電車に乗ったら解け、悲惨になる。
はるか前方を歩いていた、氷で行く手を阻まれたガリンコ号のようにノタノタと歩いている、(後姿から察するに)中年のおばさんに追いつく(この女性は大またの足跡先駆者ではなく、途中の横道から出てきたらしい)。ケモノ道みたいな歩道だから、追い越したくてもなかなか追い越せない。
こういうおばさんに限って、どうして腕を前後に大きく振って歩くのだろう。追い越すためにそばに寄ると、へたしたらコブシが股間にあたってしまう。危険だ。私の股間も、私への濡れ衣も。
猛吹雪の中で痴漢行為を働く変わり者とは思われたくない。しかも超熟女好きの。猛吹雪にもかかわらず性的衝動を抑えきれない会社員と思われたら困る。どうせ疑われるなら穏やかで暖かな日に、もっと若い女性に股間を叩かれたい(あくまで比較論である)。
ケモノ道がちょっと広くなっていたところで一気に追い越す。
追い越したときも、その老女(推定)は追い越されたことすら気づかないように、黙々とゆっくり、ピラミッド建設に携わる奴隷のように一歩一歩前に進んでいた。
吹雪の中、路で追い越す。これが越路吹雪の名の由来かもしれないと閃いた瞬間、私の気持ちも少し和らいだ(←すいません、滑りました。冬道は危険です)。
駅に着くと、これまたびっくり。
電車は定刻どおり運転している。
私が出張で空港に行かなければならないときには運転を見合わせていたくせに、すっかり疲れ果てて会社に行きたくないと思っているときには元気に規則正しく運転している。どうも腑に落ちない。
ドビュッシー(Claude Debussy 1862-1918 フランス)の合唱曲「シャルル=ドルレアンの3つの歌(3 Chansons de Charles d'Orleans)」(1909初演)の第3曲は「冬はほんとうにいやらしい(Yver,vous n'etes qu'un villain)」というタイトルだが、まったくもって、本当に冬はいやらしい。
おぉぉぉぉ~、いやぁぁぁぁ~ん、ケダモノぉ~、って感じである。
そして、この曲がどういう曲かというと、……知らない。聴いたことない。
電車に乗ると、幸いなるかな、座ることができた。
しかしやがて私に異変が起こった。胃炎じゃない、異変だ。
頭がもぞもぞするのだ。
おかしい。
暖かくなったので蝶が羽化し、私の頭の上から飛び立とうと努力したかのような感触だ。
頭に手を当ててみる。
そこにはミミズのようなものが……って、私の座席の横に立ったおしゃれっぽくないおじさんが、おしゃれっぽい革の文庫本カバーをかけた文庫本(文庫本カバーをかけているのだから、中身は少なくともアルバイト情報誌ではないだろう)を読んでいるのだが、そのカバーについている革ひものしおりが、私の頭をかすめるかかすめないかの絶妙な位置でフラフラしているのだ(私は横目+上目を極限まで駆使し、それを確認した。えらく目が疲れた)。
もし、私の毛髪の中にザリガニがいたなら、餌と間違えて間違いなくはさみを出したところだろう。
しかもそのおじさん、私にこのような多大なる迷惑をかけているにもかかわらず、まったく気づいていない。私は勇気を持って我慢することを決意した。座っていられるだけ幸せなんだ。そう考えることにしたのだ。あぁ、現実逃避。合理化。白日夢。
会社に着く。
いつもと同じように、早すぎる時間に着く。
靴の中はびちょびちょだ。
果たしてどんな臭いになっているのかな、といけないことを考えてしまう。
さあ仕事だ、仕事だ。
jobだ、jobだ。
ムチを打たれたように、いやいやながら自分を駆り立てる。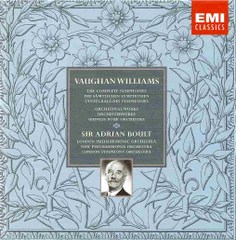 ヴォーン=ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams 1872-1958 イギリス)の8場から成る仮面劇「Job」は、仮面をかぶってする仕事の話ではない(どんな仕事だ?ふふふっ)。
ヴォーン=ウィリアムズ(Ralph Vaughan Williams 1872-1958 イギリス)の8場から成る仮面劇「Job」は、仮面をかぶってする仕事の話ではない(どんな仕事だ?ふふふっ)。
このJobはヨブだ。
ヨブは旧約聖書の「ヨブ記」のヨブである。
G.ケインズとG.レイヴェラの「ヨブ記」に、ウィリアム・ブレイクが描いた挿絵に基づく舞踊劇のための音楽であるという。作曲は1931年。
W.ブレイクが「ヨブ記」に描いた挿絵は、例えば上に載せたもので、これは「ヨブに襲い掛かるサタン」だそうだ(Wikipediaより転載)。
私が持っているCDは、ヴォーン=ウィリアムズの交響曲第7番(南極交響曲)のときにも紹介した、交響曲全集に収められているもの。ボールト指揮ロンドン響の演奏で、仮面劇「ヨブ」は1970年の録音(EMI 7243 5 73924 2 6(輸入盤))。
ところで私のジョブの方は、ずっと靴の中が乾きかけた生け花のオアシスのようで、全然はかどりませんでしたとさ。
このところ、犬の歯石取りのガムだか棒だかのTVコマーシャルがずいぶんと流れている。
あれで歯石が取れ、歯茎も丈夫になるなら、人間様にも応用できるのではないか?
そんなことを考えている、雪かき疲れの私である。
雪かきと言ってもこの土日に新たに降ったわけではない。
ベランダに高く積もっていた雪を降ろしたのだ。
だって、窓の下3分の1が覆われ、圧で窓が割れる危険もあるし、それ以上に陽の差込みが少ない。これじゃあ私、モヤシになっちゃう。
わが家のベランダ(ハウス・メーカーによるとバルコニーと呼ぶ)は、実は6畳くらいの広さがある。
家を建てたときには、何となく暮らしにおしゃれ感を醸し出しそうでいいかなと思った。バルコニーで一家団らん焼肉パーティー……。あぁ、家族団らんの虚像!
しかしそれから3ヶ月もすると、現実に直面。降雪、積雪だ。
この屋根のかかっていない余計なスペースは、1シーズンに1~2回ながらも余計な作業をもたらすことを思い知らされたのだ。
それに冬以外だって、そんなに使うもんじゃない。
たまに洗濯物を干すのに使っているだけ。
だいたい、焼肉をしたけりゃ庭ですればいいのだ。わざわざ2階でやる必然性はない。肉や野菜やタレを階段を使ってわざわざ運ぶことに何か意味合いがあるのだろうか?
ない!
ということで、贅沢な無駄なスペースの雪降ろしをしたってわけ。
バルコニーの雪降ろしは今シーズン初。
寒気と暖気の繰り返しで太古の地層のようになった雪は、けっこう固くて重い。
ぎゃぽっ!
ここで初めて気づいた。今年はバルコニーに置いてある物干しを片付けてなかった。
春にはプラスティック製の土台が崩壊してるな……
で、雪を下に落とす。
ときどき下のコニファーに雪の塊が衝突。枝が飛び散る。心が痛む。
雪を降ろしたあと、今度は地面に山になっている降ろした雪を片付ける。
それは、2階からの重力を得てさらに固く重くなっている。
プラスティックの雪かきでは歯が立たないくらいだ。
犬用のあの“棒”を雪かきに適用できないだろうか?
その雪を捨てるために運ぶ。
はいはい、十分な労働。
話は変わる。
昨日のわが家は諸事情によりケーキがあった。
私以外の人々は夕食後にそれを食べようとしていた。
私はというと、だらだらとビールをたらふく飲んでいた。
そんな私に非難の意味を込めて、妻は言った。
「あんた、いる?」
ひどい。あんたはないだろうが、おまえっ!
アンタイル(George Antheil 1900-59 アメリカ)は、未来派的手法、ジャズの用法を用いて、実験的作品を残した作曲家である(当初はピアニスト)。有名なのはバレエ音楽の「バレエ・メカニック(Ballet mecanique)」(1923-24/'54改訂)。この作品は極めて前衛的だというが、残念ながら私は耳にしたことがない。
1930年代になってアンタイルの作風は伝統的になっていくとともに、食べていくために映画音楽を作曲したりもした。
人気がでたのは1940年代。
そのころ作曲されたものに交響曲第4番「1942年」(1942)がある。
この交響曲は第2次世界大戦の悲惨さにインスピレーションを得て作曲されたようだが、聴いていて良い意味でも悪い意味でアメリカ音楽を感じさせるもので、あまり考え込まされない。終楽章のメロディーなどは心地よいほどだ。
 「1942年」というタイトルはショスタコーヴィチの第11交響曲や第12交響曲のタイトルを思い起こさせるが、ショスタコーヴィチのようにドロドロしていない。言葉悪く言えば深遠さに欠ける曲だが、逆境でも朗らかなアメリカ人気質みたいなものが感じられて、一度は聴いてみても損はない。
「1942年」というタイトルはショスタコーヴィチの第11交響曲や第12交響曲のタイトルを思い起こさせるが、ショスタコーヴィチのようにドロドロしていない。言葉悪く言えば深遠さに欠ける曲だが、逆境でも朗らかなアメリカ人気質みたいなものが感じられて、一度は聴いてみても損はない。
CDはクチャル指揮ウクライナ国立響のものを(1998年録音。ナクソス8.559033)。
カップリングは交響曲第6番ほか。
そして、“あんた”は無事ケーキにありつけましたとさ。
吉松隆センセの著書「クラシック音楽は「ミステリー」である」について、先日書いた。
この本のなかで、ショスタコーヴィチの交響曲第7番の最後では、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」の動機が繰り返し吹き鳴らされていることについて触れられている。
ベートーヴェンの「運命」と言えば、シュニトケの「エスキース」のなかで「運命」が鳴りひびき、それまでの「老人と子供のポルカ」を思わせる雰囲気を蹴散らすことを、やっぱり先日書いた。 「運命」はあまりにも有名だが、昨日の記事で取り上げたファリャの「三角帽子」にも出てくるし、ブラームスの交響曲第1番にもこの動機のリズムが執拗に現れるなど、後世の作曲家に広範囲にわたって影響を及ぼしている。
「運命」はあまりにも有名だが、昨日の記事で取り上げたファリャの「三角帽子」にも出てくるし、ブラームスの交響曲第1番にもこの動機のリズムが執拗に現れるなど、後世の作曲家に広範囲にわたって影響を及ぼしている。
そのベートーヴェンの交響曲第5番の冒頭、「運命動機」は左の写真のものだが(ケイサイスコアは全音楽譜出版社のもの)、この2小節の4音から成る単純な動機が、息切れしちゃわないで延々と影響を及ぼしているのである(はいはい、そっちのドウキは動悸です)。
そして私は吉松隆と「運命」を、近所の娘さんに頼みもしないのに縁談を持ってくるお節介ババアのように、結び付けたい。
いや、もう繋がっている……
ということで、吉松隆の交響曲第5番。
現在までに吉松は5曲の交響曲を書いている。
それぞれの作曲年は、
第1番(カムイチカプ交響曲)Op.40 1990年
第2番「地球にて」Op.43 1991年
第3番Op.75 1998年
第4番Op.82 2000年
第5番Op.87 2001年
である。
吉松隆は自分で交響曲第5番を書くにあたり、ベートーヴェンの「運命」のモティーフ(動機)で始め、最後はハ長調の主和音(ドミソ)で終わる、という夢をもっていたという(詳しいことは吉松隆のホームページに書かれている)。
そして夢をかなえちゃいました。
いや、夢のレベルを超え、交響曲やドミソを封印した現代音楽全盛時代への復讐(反抗?)として、吉松はこれを実現した(ということでよいのでしょうか?)。
始まりは運命動機のジャジャジャジャーンッ!聴いていて恥ずかしくないと言えばうそになる。
それほどジャジャジャジャーンッである。 ただ、私にはこれがベートーヴェンの「運命」というよりは、ドヴォルザークの交響曲第8番の第2楽章を思い起こさせる。優しくてのどかに第2楽章が始まってからほどなくして、オーケストラが強奏する箇所だ(31小節目。掲載したスコアは全音楽譜出版社のもの)。
ただ、私にはこれがベートーヴェンの「運命」というよりは、ドヴォルザークの交響曲第8番の第2楽章を思い起こさせる。優しくてのどかに第2楽章が始まってからほどなくして、オーケストラが強奏する箇所だ(31小節目。掲載したスコアは全音楽譜出版社のもの)。
あるいはこれも「運命の動機」を意識しているのか?
吉松隆は交響曲第5番の前年に第4番を書いている。
作曲者の言葉によると、小型の「パストラル(田園)・トイ(オモチャの)・シンフォニー」の性格を持った交響曲、である。
この曲のCDを聴いたときは、けっこう衝撃を受けた。
なんて良い曲だろう!と。
そして翌年に書かれた第5番。
CDが出たときは、即買いに行った。
ところで、ベートーヴェンは第5番を書きあげる直前から、次の交響曲第6番「田園」に着手している。
吉松は、彼の「田園」とも言える第4番を作曲する前に別の交響曲に着手していたが、第4番の方が先に完成。そのあとに途中になっていたものを再構想して第5番として書きあげた。
ふむ。
5番というナンバーを与えるために、わざと中断したのかな?
こうやってみると、ベートーヴェンの第5番「運命」と第6番「田園」の関係と同じように、曲の番号と性格は逆になるが、吉松の第4番と第5番がペアとして位置づけられる格好に偶然にも(?)なっている。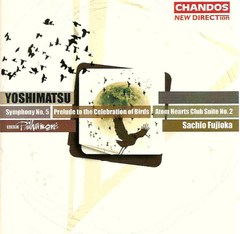 さて、CDを買いに走った私だが、第4番を聴いたときほどの感動や感銘は受けなかった。
さて、CDを買いに走った私だが、第4番を聴いたときほどの感動や感銘は受けなかった。
かなり肩透かしを食らった感じだった。
第5番も吉松サウンドが美しく炸裂するし、独特の甘さや優しさもある。
ただ、「運命の動機」がどうもそれを安っぽくしている感じがする。
輝かしく、最後なんかは気持ちを煽られるんだけど、我を忘れるほどじゃない。いい曲なんだけどね。あのとき期待しすぎた反動をずっと引きずっているのかしら、アタシ。
曲は4つの楽章から成り、作曲者によれば第1楽章は「分裂症的なアレグロ」、第2楽章は「冷笑的で悪魔的な乾いたスケルツォ」、第3楽章は「女性性によせる悲歌風のバラード」、第4楽章は「錯乱した舞踏としてのフィナーレ」である。
↑ あいかわらず、巧いなぁ。
分裂症的で悪魔的な錯乱した私はすっかり感心しちゃう。
ところで交響曲第5番を発表してからもう10年になろうとしている。
このブランクは吉松隆にしては異例。
もう交響曲は書かないつもりだろうか?
いや、当然「第9」に対応するところまでは書き続けますよね?
さて、第5番のCDは藤岡幸夫/BBCフィルのシャンドス盤(2002年録音)。
シャンドスの吉松隆シリーズである。
他に「アトム・ハーツ・クラブ」組曲第2番Op.79aと「鳥たちの祝祭への前奏曲」Op.83が収録されている。
でも、もしかするとこの交響曲第5番、別演奏で聴くと私のこの曲に対する物足りなさは払拭される可能性もある。別録音はほとんど絶望的に期待できないけれど……
昨夜18:00から、札幌のパークホテルで民主党・北海道の新春パーティーとやらが開かれた。
たまたま用があって、17:30過ぎに地下鉄で移動し中島公園駅から地上に出ると、警察による厳重な警備態勢。小沢一郎が来るからだ。
雪でただでさえ道が狭まっているのにこの警備だ。
ひどく渋滞していた。
その中島公園から1本か2本、すすきの寄りに戻った東西の道路。
その道も雪で車がすれ違うのがやっとという狭さになっていたが、こともあろうにそこで客待ちなのかどうか知らないが、ハザードをつけた空車のタクシーが停車している。
後ろから来た車は、対向車線も車が連なっているのでそれを追い越せない。
対向車線のタクシーの運転手がさすがに「そこ停まるな!」と、停車したままゾウガメのように居座っているタクシーに、窓を開けて怒鳴っている。停車しているタクシーの後ろの車は、困惑したままだ。
ところがその停車タクシーの運転手は「なんでだよ!」みたいな表情で、逆に注意したタクシーの運転手をにらみ返し、数十センチ前に動かしただけ。
まったく、こいつ、プロのドライバーっていう意識がないのだろうか。
私は決めた。
この大迷惑停車をしていたSKグループのピンク色の車体の会社の車には絶対乗ってやらない、と。そうです、札幌のある地域名が社名になっているところです。
雪道の話、というか、これはショッピング・センターの駐車場で見かけた話。
昨日のことだ。
スーパーの駐車場で、通路と駐車スペースの境目がわかるように置かれたカラーコーン(雪が積もると地面に引かれたラインがまったく見えなくなるので)。
そのカラーコーンを轢き、それを腹に引っかけたままお帰りになった車を見かけた。
路面が凍っていたため、コーンも心地よさそうだった、ってことはないが、あのもみじマークのじいさん、そんなんだったらもう車の運転、やめて欲しい。
そのコーンで思い出したのが、ファリャ(Manuel de Falla 1876-1946 スペイン)のバレエ「三角帽子(El Sombrero de Tres picos)」(1918-19)。
コーンは三角じゃなくて円錐形だが、正面から見たら三角形に見える。
それにコーン型の、いわゆるとんがり帽子、クリスマスの夜にノリスケさんがそれをかぶってサザエさんちを訪問するような、あの魔女帽子のことを、どうしても連想してしまう。三角帽子という言葉からは。
でも実際には全然違う。
ウィキペディアで確認してほしい。
私も今回やっと知ったのだけど。というか、知ろうという学習意欲がなかったんだけど。 2幕から成るバレエ「三角帽子」の台本は、ペドロ・アントニオ・デ・アラルコン(1833-91)の同名の小説からグレゴリオ・マルティネス・シエラが書いた。
2幕から成るバレエ「三角帽子」の台本は、ペドロ・アントニオ・デ・アラルコン(1833-91)の同名の小説からグレゴリオ・マルティネス・シエラが書いた。
ファリャは1916年から17年に、パントマイム「市長と粉屋の女房(El corregidor y la molinela)」を作曲していたが、ディアギレフの勧めでバレエ音楽に改作した。
三角帽子というのは権力の象徴で、これをかぶる市長が粉屋の女房に言いよるものの……という喜劇。
クラシック音楽においてスペインの作曲家というのはそう多くない。
ファリャはスペイン民族主義楽派であり、この「三角帽子」も異国情緒あふれた楽しく色彩的な音楽となっている。といっても、親しみやすい中に も過激さがあって刺激的でもある。
も過激さがあって刺激的でもある。
バレエは、序奏(ここではオーケストラ団員が「オレッ!オレッ!」と掛け声をあげるが、かつて札響の定期で聴いたときには、楽員が恥ずかしそうな表情をしていた)のあと、第1幕に入る。第1幕は、「昼下がり」、「粉屋の女房の踊り」、「葡萄の房」の3曲。
第2幕は「隣人たちの踊り」、「粉屋の踊り」、「市長の踊り」、「終幕の踊り」の4曲。
「三角帽子」には第1幕、第2幕それぞれを抜粋して作った2つの組曲があり、特に第2組曲がポピュラーだが、ぜひとも全曲を聴きたいところ。全然退屈しないですから!
シュニトケの「エスキース」というとっても楽しい曲のことを書いたとき、「老人と子供のポルカ」チックな音楽がベートーヴェンの交響曲第5番の「運命動機」の登場でさえぎられることを 書いたが、実はこの「三角帽子」でも「運命動機」が使われている。
書いたが、実はこの「三角帽子」でも「運命動機」が使われている。
第2幕の「粉屋の踊り」のなかだが、ドアをノックする音を「運命動機」で表現しているのである(この部分は組曲には入っていない)。ちょいとしゃれたユーモアだ。ホルンが吹く、その部分のスコアを載せておく(掲載スコアは日本楽譜出版社のもの。写真は2枚にわたっているが、楽譜は上から下へ続く)。
演奏で私が気に入っているのはプレヴィン/ピッツバーグ響、メゾ・ソプラノ独唱がフレデリカ・フォン・シュターデによる演奏(1981年録音。フィリップス)。ノリがよくてしゃれっ気があって、この曲の演奏にぴったりと思っている。
しかし、現在のところ廃盤のよう。
だとしたら、次にお薦めなのはデュトワ盤かな……
プレヴィンといったらジャズからクラシック音楽へと転向した人。私がクラシック音楽を聴き始めたころにはすっかりクラシック界の人になっていた。
このあいだ、何かの本でジャズの話が書いてあり、プレヴィンの名前が出てきた。そんなところでプレヴィンの名を目にするなんて不思議な感じがした。
しかし、その本が何だったかさっぱり思い出せない。最近の出来事なのに……
村上春樹の本だったような気がするが……
大学を卒業し今の会社に就職した時に、何がすごいと思ったかというと、女性社員がそろいもそろって皆綺麗、あるいはかわいい、ということだった(もちろん何事もそうであるように、例外もあった。少なからず)。
どうしてそう思ったか?
ちょいと考えればすぐにわかること。
要するに、私が化粧をした女性に慣れていなかったせいだ。
私の通っていた大学では、あまり化粧をしている“女子大生”がいなかったのだ。だからといって、その代わり男子学生が化粧好きだったということでもない。
ただ私の持論は、ベースが良くないといくら化粧をしたところで化け方に限界がある、であった。
しかし昨今の結婚詐欺女の写真を見ると、その自信は大きく揺らぐ……
学生の時にかわいいと人気者だった女の子が、だからといって化粧をするともっと良くなるかというと、必ずしもそうでないこともあるようだ。
化粧映えする顔とそうでない顔があるらしい。
女性の化粧顔で、私がちょっぴり好きになれないのは“粉を吹いている”ような白塗り化粧だ。
これってノリの問題なのだろうか?
そういえば浅草は雷門のすぐそばにそこそこ有名な天ぷら屋がある。
とてもおいしい天ぷらを食べさせてくれる。
そして、ここの店の“お姉さま”がたは、そろいもそろって、マイケル・ジャクソンも食欲を失ってしまいそうなほど顔が粉っぽくて真っ白い。厨房で天ぷら粉に顔を埋めてきたかのようだ。なかなかすごい。
これが天ぷら屋ということをアピールする広告戦略の一環だとしたら、すごい!
やめてくれ。
ネタのエビの活きが悪いかもしれないと思ってしまう。
ラフマニノフ(Sergei Rachmaninov 1873-1943 ロシア)の合唱曲集「3つのロシアの歌(Three Russian Songs)」Op.41(1926)。歌詞はロシア民謡による。
3曲から成るこの合唱曲集の第3曲は「赤らめた頬におしろいを塗ってよ」というタイトルである。自分で塗れよ……
これは三省堂の「クラシック音楽作品名辞典」に書かれている邦訳名。
ところが手持ちのCDに書かれている曲名は「早く早くお化粧を落として」となっている。
化粧について何もわからないアタシですが、これって真逆の意味のように思うんですけど……
ちなみにCDに書かれている英訳名は“Quickly,quickly,from my Cheeks the Powder off”である。ということは、落とすのかい?
浮気が見つかった若妻が潔白を装うものの、うまくだましきれずに、夫の「絹のムチ」を覚悟するという内容らしい。「絹のムチ」っていうのもよく理解できないけど、いずれにしろ化粧を塗るのか落とすのか、よくわかりません、私には。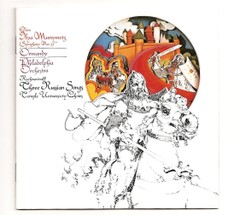 私が持っているCDはオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団、テンプラ、いや、テンプル大学合唱団による演奏(1973年録音。RCA)で、グリエールの交響曲第3番「イリヤ・ムーロメッツ」の“余白”に収録されている。
私が持っているCDはオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団、テンプラ、いや、テンプル大学合唱団による演奏(1973年録音。RCA)で、グリエールの交響曲第3番「イリヤ・ムーロメッツ」の“余白”に収録されている。
ところで、タワーレコードのサイト・リニューアルに伴い、過去記事のCD紹介をクリックしても直接商品ページに飛ばず、サイトのトップ・ページに飛ぶ状況となった。
すまない。
でも、膨大な記事数なので、過去のブログ記事は修正はしませんです。
ごめん……
絹のムチかぁ~
※ 2023年5月より、過去のブログ記事のタワレコへのリンクを修正(削除)する作業を遅々と進めています。
おととい雨が降ったかと思うと、昨日は吹雪模様。
前日に降った雨は、新たな雪の下で、望んでもいないのに「かっちかっちやで」のスケートリンク状態。ちょいと気を抜くとスッテンコロリンしそうで危なっかしいったらありゃしない。
そういう道を歩くとき、自分でも理解できないような箇所に力が入っているのだろう。内腿(うちもも)の深部に“だる痛さ”が蔓延している。
そういう吹雪模様で、しかもすっごく冷え込みが厳しいにも関わらず、昨日の夜はナシニーニ(初登場!♂)と食事。
ナシニーニは「たまにはイタ飯を食べましょう」と言ったが、目に入った店に安直に入ろうとしたが混んでいて即断念。いや、席は空いていたようだが、店に足を踏み入れても誰一人出迎えに来てくれない。こんなんじゃ席についたって、ずっと招かざる客扱いされそうだ。だったらイカ飯の弁当を買って立ち食いした方がまだましだ。腹が立たない分。
「じゃあ焼き鳥にしましょうか?」と私が提案すると、ナシニーニは「ええ、いいですよ」と、まったくいいですよじゃないような返事をした。私だって別に焼き鳥を食べたいわけじゃないのだ。ただ、いつまでも無言で向かい合っているわけにはいかないので、そう言ったまでだ。
ということで結局は洋食屋に行って、ソーセージとハンバーグとビールという子供が喜びそうな(ビールはともかく)食事となった。ナシニーニだけは生ガキを食べていたが、なんとなくエッチっぽかった。カキの姿が……
そのあと別な店に行った。
スナックとバーを掛け合わせてルートで二乗根を求めたような、何とも形容しがたい形態の店だ。しかし、妖しくなくて健全な雰囲気で落ち着ける。落ち着けるのは空いているからで、店としては困ったもんなんだろうけど私たち客にしてみたらとても居心地が良い。この店こそナタオーシャとカトナーリャがいる店で、店長の名はカチャカポコナという(一応日本人)。
予想に反し長居してしまった。
ナシニーニがどうしてもカラオケを歌いたいと、だだをこねたからだ。
カトナーリャは、私には理解できない前衛音楽のような歌を歌っていた。あの歌よりもジョン・ケージの作品のほうが、私には馴染める。
ナタオーシャはちあきなおみの「喝采」を歌っていた。曲の性格上、私はナタオーシャに喝采した。
最後の最後になぜかキャンディーズの「微笑がえし」の話となり、この歌の歌詞にはそれまでのキャンディーズの歌のタイトルが回顧されるように折り込まれている、ということを再確認するために、こともあろうに私とナシニーニとでデュエットしてしまった。なんだか、それまでの楽しい時間を自らぶち壊してしまったような気持ちになってしまった。
ビルを出たときには、このあいだほどじゃないにしても、けっこう雪が積もっていた。
すさんだ気持ちに雪。
やれやれ……
でも前のときのように、帰宅してから夜中に雪かきをするという気力も知力も筋力も視力も脚力もなく、そのまま寝てしまった。考えてみれば酔っ払った状態で夜中に雪かきをするというのはかなり危険な行為だ。ファイターズの小林繁コーチだって心不全で死んでしまったのだ。スポーツに縁のない、細いツララのようにか弱い私ならどうなるのか、想像するだけで恐ろしい。
朝……
寝不足……
眼球の裏側でティンパニ奏者がマーラーの交響曲第7番終楽章の冒頭を叩いているかのような響きがある。ドンドコドンドン、ドンドコドンドン……
やれやれ……
当然のことながら、気持ちだって明るくない。
あまり食欲もなく、ご飯は茶碗で2杯しか食べられなかった。
おかずのベーコンも3枚しか食べられなかった。
ふと、私の鼓膜の裏側でホルンの柔らかなメロディーが流れる。
幻聴ではない。
頭歌だ(鼻歌という言葉があるのだから、頭の中でメロディーをなぞることを頭歌―この場合ズカという読みにするとへんてこで良いような気がする―と呼ぶことにしても、誰も怒らないと思う)。
その曲は、「ライト・オブ・マイ・ソウル(Light of my soul)」
何年か前に学生の吹奏楽コンクールで耳にし、気に入ったのでCDを買った。
このときまで気づかなかったのだが、CDショップってけっこう吹奏楽のCDが置かれている。中途半端なショッピングセンターの中に入っている、花屋ぐらいの広さしかないCD店でさえ、吹奏楽のCDが必ず何枚か置かれている。マーラーの交響曲第7番が棚になくても(棚に置く気すらなくても)、「ブラバン甲子園」みたいなCDは置かれているのである。それだけニーズがあるのだろう。ブラバン人口は、予想よりもはるかに多いようだ。
「ライト・オブ・マイ・ソウル」の作曲者はD.ギリングハム(David Gillingham 1947- アメリカ)。Wikipediaによるとギリングハムは、現代吹奏楽作曲家の神様的存在のリード(Herbert Owen Reed 1910- アメリカ)などに作曲を師事したという。 「ライト・オブ・マイ・ソウル」のライトはLightなので、“我が魂の権利”、じゃなく“我が魂の光”っていうような訳になるんだろう。自信はまったくないけど。
「ライト・オブ・マイ・ソウル」のライトはLightなので、“我が魂の権利”、じゃなく“我が魂の光”っていうような訳になるんだろう。自信はまったくないけど。
朝食を食べたから私の気持ちが少し明るくなったのかもしれない。実にピュアな人間だ。私は。
賛美歌の主題を変奏的に扱っているそうで、そのためか非常に美しく親しみやすい。
ただ、中間部で打楽器群が爆発する。
この部分、私にはない方が良いように思うのだが、私にはそんなことに注文をつける“権利(right)”はないし、吹奏楽部のパーカッションの人たちも活躍させるように書かれているのかもしれない。
でも今朝も、頭歌がその箇所にさしかかったら、私の眼球の裏側ではドッカン、ズッギュン、バッカン、チャカポコチャッって感じで、痛たたたたぁ~となってしまった。
CDは「CAFUAセレクション2007 吹奏楽自由曲選『メトロプレックス』」というタイトル。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。CDの性格上(毎年新しいのが出ている)古くなったものはそのまま終売になって再発売されることはないと思う。
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
- 12音音楽
- J.S.バッハ
- JR・鉄道
- お出かけ・旅行
- オルガン曲
- ガーデニング
- クラシック音楽
- コンビニ弁当・実用系弁当
- サボテン・多肉植物・観葉植物
- シュニトケ
- ショスタコーヴィチ
- スパムメール
- タウンウォッチ
- チェンバロ曲
- チャイコフスキー
- ノスタルジー
- バラ
- バルトーク
- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽
- バロック
- パソコン・インターネット
- ピアノ協奏作品
- ピアノ曲
- ブラームス
- プロコフィエフ
- ベルリオーズ
- マスコミ・メディア
- マーラー
- モーツァルト
- ラーメン
- ルネサンス音楽
- ロマン派・ロマン主義
- ヴァイオリン作品
- 三浦綾子
- 世の中の出来事
- 交響詩
- 伊福部昭
- 健康・医療・病気
- 公共交通
- 出張・旅行・お出かけ
- 北海道
- 北海道新聞
- 印象主義
- 原始主義
- 古典派・古典主義
- 合唱曲
- 吉松隆
- 名古屋・東海・中部
- 吹奏楽
- 周りの人々
- 国民楽派・民族主義
- 変奏曲
- 多様式主義
- 大阪・関西
- 宗教音楽
- 宣伝・広告
- 室内楽曲
- 害虫・害獣
- 家電製品
- 広告・宣伝
- 弦楽合奏曲
- 手料理
- 料理・飲食・食材・惣菜
- 映画音楽
- 暮しの情景(日常)
- 本・雑誌
- 札幌
- 札幌交響楽団
- 村上春樹
- 歌劇・楽劇
- 歌曲
- 民謡・伝承曲
- 江別
- 浅田次郎
- 演奏会用序曲
- 特撮映画音楽
- 現代音楽・前衛音楽
- 空虚記事(実質休載)
- 組曲
- 編曲作品
- 美しくない日本
- 舞踏音楽(ワルツ他)
- 行進曲
- 西欧派・折衷派
- 読後充実度
- 邦人作品
- 音楽作品整理番号
- 音楽史
- 駅弁・空弁
© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」

