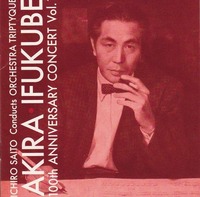 先日発売されたCD「伊福部昭 百年紀 Vol.1」。
先日発売されたCD「伊福部昭 百年紀 Vol.1」。
そのなかから「国鉄」組曲。
いまの若者諸君は、もはや“国鉄”って言葉を知らない人の方が多いかもしれない。
鉄道マニアとかなら、JRの電車が国鉄色で期間限定運転というニュースを聞くと、ウホウホ喜んじゃうってことがあるが、鉄道に関心がなくて、しかもピチピチの若い子と来た日にゃ、「クニテッショクってなぁに?」って、相対性理論について理解できないのと同じくらいキョトンとしちゃう可能性がある。しかもこう書くと、テクニシャンに似てるという新たなる発見!
にしても、国鉄時代の列車の乗り心地ってひどかった。
特急車両はともかく、急行や普通列車の、あの窮屈さ耐久レースを強いられているようなボックス席。客のことをなんも考えてなかった。
昔、根室8:30発函館行のニセコ2号っていう急行があって、何度か札幌まで利用したことがあったが、札幌に着くのが18時近く。石勝線がまだ完成していなくて、根室→釧路(ここで30分ほど停車し増結。ここで駅弁を買わないと昼飯を食いそびれてしまう)→帯広→富良野→滝川→札幌という根室線と函館線経由の運転。
向かいの人とひざがぶつからないわけがないあの狭いボックス席で、ただただ耐えるしかない。駅弁を食べている姿を知らない人の目の前にさらけ出さなきゃならないが、じっと我慢するしかない。食べたくないが、冷凍ミカンをおすそ分けされたら、過剰に感謝の意を表して受け取らざるを得ない。
私は札幌で降りるからいいものの、そのまま小樽→倶知安→長万部→函館と終着駅まで行く人は(どれぐらいの割合でそういう人がいるのかわからないが)、着いたら立ち上がれるのが奇蹟だというくらい疲れるはずだ。
しかも函館着は23時ころだったわけで、そこから青函連絡船に乗り継ぐ人の方が多かっただろうし……。昭和の人たちって元気だったんだなぁ。
もっとも私の場合は、父親が一時期根室に住んでいたのでこのような経験をしたわけで、これが釧路だったなら最初っから特急おおぞらを利用しただろう。間違いなく。
「国鉄」組曲(Japanese National Railways,suite)は、伊福部昭(Ifukube,Akira 1914-2006 北海道)が手がけた国鉄の記録映画3本から12曲を組曲化したもの。
2014年2月に行なわれた伊福部昭百年紀実行委員会主催のコンサートで披露されたが、この日のコンサートではいくつかの映画音楽の組曲が演奏された。それらの組曲は基本的に元の映画音楽用の楽譜を忠実に再現することを念頭に置いて作ったという。
「国鉄」組曲で音楽が使われた3本の映画とは次のとおり。
・ つばめを動かす人たち (1954:日映科学)
・ 雪にいどむ (1961:日映科学)
・ 国鉄~21世紀を目指して(1966:学研)
一応補足しておくが、つばめというのは特急列車の名前。
1964年の東海道新幹線開業まで東海道線を疾走した列車である。
伊福部の他の映画でも使われているメロディーが満載。にしても、機関車の力強さや厳しい気候との戦いなどを表現するのに、伊福部音楽が見事にはまっているのがわかる。
演奏をとやかく言うのはのは野暮ってもの(が、スケール感は大きくないが決して悪い演奏ではない)。
貴重な音源をこのように聴けることに非常に大きな価値がある。
ほら、“ゴジラだけでなく数々の特撮映画や黒澤映画の音楽も担当して日本映画の黄金期を支えた巨匠・伊福部昭による珠玉の音楽をフルオーケストラで堪能できる貴重なCD”って、↓ のタワレコのサイトにも書いてあるでしょ。
齊藤一郎指揮オーケストラ・トリプティーク。
2014年ライヴ。スリーシェルズ。
“21世紀を目指した”国鉄だったが、1987年3月31日が最後の日になってしまった。
さて、ご案内のとおり、この「読後受実度 84ppm のお話」での記事の新規投稿は本日で最後となります。
明日以降は、ブログ名も大胆にリニューアルした「新・読後充実度 84ppm のお話」で記事を更新してまいります。
引き続き新ブログをご愛読いただくことをお願い申し上げます。
なお、今日までの記事はこちらで引き続きご覧いただけます。
June 2014
 若き日のマゼールがベルリン放送交響楽団を振った、モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-91 オーストリア)の交響曲第40番ト短調K.550(1788)ならびに交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター(Jupiter)」(1788)。
若き日のマゼールがベルリン放送交響楽団を振った、モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-91 オーストリア)の交響曲第40番ト短調K.550(1788)ならびに交響曲第41番ハ長調K.551「ジュピター(Jupiter)」(1788)。
録音は1966年。
先日の札幌出張の際、ポイント15倍のチケットを握りしめてタワレコに行ったが、店頭に並んでいるこのCDジャケットのマゼール様の視線を股間あたりに熱く感じたような気がして購入した。
タワーレコードの紹介文 ↓。
第40番については“大胆なまでの強烈な表情づけ”、第41番には“激しい緩急の対照と個性的なアクセント”と書いてあるが、まったくもって巧い表現。
私としては異議なし、です。
録音のせいもあるのだろうが、音質はややサメ肌風。が、それはあまり問題にならない。
マゼールは聴き手をうっとりさせたり、感傷に浸らせてくれない。スポーティーかつ締まった演奏を貫く。オーケストラの響きは厚いが、もたつくところはない。
私はモーツァルトの演奏スタイルではピリオド奏法の方が好きだが、このモダン演奏は弛緩することなく退屈させられない。若々しいはつらつとした姿勢に心を捉えられる。勝手な思い込みかもしれないが、「打倒!カラヤン/ベルリン・フィル」という意気込みもあるのかもしれない。
ジャカジャカしたピリオド演奏は落ち着かないが、モダン演奏でも甘ったるいモーツァルトはちょっとねぇという人には、格好の餌食、いや、格好の1枚。
なお、交響曲第40番にはクラリネットが編成に加わらない版と、クラリネット入りの版の2種があるが、マゼールはクラリネットなしの第1稿を用いている。
Tower Records Vintage Collection +plus Vo.18(原盤フィリップス)。
お 知 ら せ
当ブログ 「読後充実度 84ppm のお話」 は、21日(土曜日)をもって、新規記事の投稿を終了いたします。
22日からは、「新・読後充実度 84ppm のお話」として、装い新た、内容未進歩のままスタートいたします。
これまでの当ブログの記事は“ブログ人”のサービスが終了する11月末日までそのままご覧いただけます。12月以降は、別な形でお読みいただけるよう残す予定です。
みなさまには大変ご迷惑とお手数をおかけいたしますが、今後ともご愛読のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、「読後充実度 84ppm のお話」は「読後充実度 85ppm のお話」と名前を変えるので投資しませんかという勧誘電話があったとしても、当ブログとは一切関係がありませんのでご注意ください。
また、新ブログへの移行に伴う私の悩み、苦労、憤り、腹痛などの裏話については、後日改めて皆様への陳謝をこめて詳しくご報告申し上げる予定です。
突然のことで -その点では“ブログ人”が終わるという突然の案内以上に突然で、私の罪は重いと自覚しております -深くお詫び申し上げます。
曇天の朝、急に決意した霧~散・記
 月曜日の夜に自宅に帰って、即寝。
月曜日の夜に自宅に帰って、即寝。
なぜなら、お酒を飲んで帰ったから。
夜中は寒くて目が覚めた。
というのも、かけるための寝具を私はなぜかすべて蹴り落としていたから。
起き上がり別室に行き、この季節なのに“した”あとはブルブルと震えて、そのあとタオルケットに春巻のアンのようにくるまって寝た。
翌朝。
いつもどおり5時前に目が覚める。
が、空は暗く鉛色。そして雨上がりですべてが濡れている。
とても庭の早朝作業をするコンディションではない。
それでも、バラがいくつか咲いているのが窓から見えたので、2本線入りのジャージのズボンを履いて、上はシャツの上にそのままジャンパーをはおり、おっとその前にキッチンあたりにアリが侵入していないかチェックしたが生体反応は私が見たところなかったので一安心し、玄関に向かってサンダルを履いて、庭を歩いた。庭といっても数歩歩けば抜けきってしまうような広さだ。わが家の庭がメビウスの帯でなくて、それでも良かったと思う。一生かかってもメビウスの帯の上を歩き続けるアリ。そんな絵を思い起こしてしまった。
レディ・エマ・ハミルトン。
前回帰宅したときにつぼみだったものは、もう散っていた。
次のつぼみがいくつかあったが、この子はつぼみ以外を私に見せようとしていないのではないかと、ちょっと悲しい気持ちになる。
このとき咲いていたのはブルー・フォー・ユー(写真)とオールド・ブラッシュ・チャイナ。
が、美しさに見とれようとしたとき、私はブルーな気持ちになった。
というのも、葉に草だんごを極小化したような物体がいくつかのっかっていたから。
覗きこむと、その上の葉の裏にそれなりに立派な毛虫がいるではないか!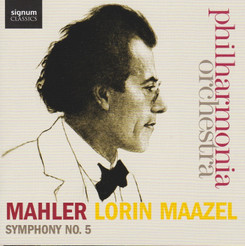 バラに毛虫が発生することはこれまでもあったが、ここまで大きくなってることはそうそうなかった。
バラに毛虫が発生することはこれまでもあったが、ここまで大きくなってることはそうそうなかった。
他も見渡すと2匹発見。無毛症の小さな毛虫、わかりやすくいえばイモムシ・アオムシ系のものも発見。
バラは雨で濡れていて、こんなときに殺虫剤を散布しても効果は薄いが、それでもいまここに生存しているやつらに直接かかれば駆除はできるだろう。
私はオルトランとスミチオンを混合し、さらに殺菌剤のサプロールも加えて、マーラーの第5の第1楽章、つまりは葬送行進曲を口ずさみながら散布した。
その後雨が降り出したが、きっとやつらはもがき苦しみ、亡くなったに違いない。
マーラー(Gustav Mahler 1860-1911 オーストリア)の交響曲第5番嬰ハ短調(1901-02。その後たびたび管弦楽配置を変更)。
今日はマゼール指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏を取り上げる。
この演奏、威勢が良くて(ノーテンキにバカ騒ぎしているという意味ではない)シャープな仕上がり(C sharp minorだからというつまらない洒落ではない)。オーケストラをたっぷり歌わせ、また強弱のアクセントを強調しており、それはまったく奇異ではないが、ある種ユニークなもの。聴けば聴くほどはまる。
たとえば、第1楽章の冒頭の葬送ファンファーレの緊張感も、奏者の緊張そのものが音になっているかのよう。この楽章の最後の1音も、他にはあまりないような響き。とどめ!って感じだ。
第4楽章の弦は、なぜかあまり美しくない。ざらついたのもいいじゃないの、ってことか。
その分、第5楽章で伸びやか、かつ、ダイナミックな演奏を聴かせてくれてるし。
なかなかカッコイイ、お薦めの1枚である。
2011年ライヴ。signum。
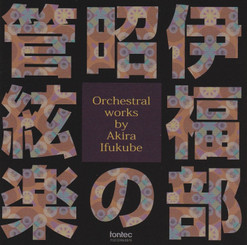 小倉朗(Ogura,Roh 1916-1990 神奈川)という作曲家をご存知だろうか?
小倉朗(Ogura,Roh 1916-1990 神奈川)という作曲家をご存知だろうか?
私はこの人の曲を1曲だけ知っている。「弦楽合奏のためのコンポジション」(1972)という作品である。作曲されてから数年後のことだと思うが、札響の“ほくでんファミリーコンサート”(札響の第2の定期演奏会とも言われている)で聴いたのだ。
どんな曲だか覚えていない。よくわからなかった。つまり楽しめなかった。
その小倉朗と伊福部昭(Ifukube,Akira 1914-2006 北海道)、吉田秀和の対談記事が「文藝別冊 伊福部昭」(片山杜秀責任編集)に収められている。
東宝交響楽団の機関誌「シンフォニー」1949年1月号に掲載されたもので、タイトルは「現代音楽をめぐる新春放談」。
小倉と伊福部が喧嘩になるんじゃないかというくらい、緊迫したやりとりだ。
伊福部ファンというひいき目を差し引いても、私は小倉の発言に悪意、意地悪を感じる。伊福部を小ばかにしている。知性のない音楽、田舎者の書いた音楽。小倉は伊福部をそのように見下しているのだ。
このころの小倉はドイツ古典派信奉者。ドイツ古典派こそが最高であり、自らの価値基準をそこに置いていた。いま読むと、それがまた痛々しくもある。
小倉は忘れ去られてはいないが、今や伊福部とは比べ物にならないほど名を残してはいない。伊福部のスタンスが、伊福部の生命力あふれる音楽が、いまでは小倉よりもはるかに支持されている。
伊福部はこういう批判にじっと耐えてきたのだ。そう思うと、まったくもって大人物だったと、あらためて敬服する。
先日紹介した筒井信介著「ゴジラ音楽と緊急地震速報」には、次のような記述がある。
戦前では、非アカデミックなものとして批判され、戦後は“過去の遺物”として無視されたのだ。
こういった状況を、伊福部昭は自虐的な意味も込めて「止まった時計」に喩えた。すなわち、泊まった時計は、一見、時間の流れから取り残されているように見えるが、少なくとも一日に二度は正しい時刻を指す、というわけである。
なんだか、胸がジ~ンとする。
この対談が掲載された前年、つまり対談が実際に行なわれた年ということになるだろうが、その1948年に伊福部が作曲したのは「ヴァイオリン協奏曲」(ヴァイオリン協奏曲第1番の初版)、バレエ音楽「サロメ」、同「エゴザイダー」である。映画音楽は6本分書いている(伊福部昭が映画音楽を最初に書いたのは1947年のことで、その作品は「銀嶺の果て」。この47年には他に「幸福への招待」という映画の曲も手がけた)。
バレエ「サロメ(Salome)」。上記のように1948年に作曲されたが、1987年に演奏会用に改訂された。
前に、山田一雄/新星日本交響楽団による改訂版の初演ライヴを取り上げているが、今日は岩城宏之/東京都響の1990年ライヴをご紹介しておく。
この演奏もすばらしい。岩城は鳴らすべきところはガンガンとオケをドライヴする。しかし音が濁ることはなく、一本調子にもならない。妖艶さもたっぷりだ。
岩城、やるじゃん!っていう名演。というのも、長らく札響の音楽監督を務めていた岩城の演奏はずいぶんと聴いてきたが、どこか一本調子というか、コクがないというか、そういう印象をもっていたから。
伊福部の「日本狂詩曲」や「ラウダ・コンチェルタータ」、この「サロメ」を聴いて、おやっと思ったのだ(良い方に)。
「文藝別冊」にはこの作品についての伊福部の話が載っている。
…… オリジナル版作曲の際には、ダンサーの体力上の制約もあって、音楽としてもっと書き込みたい、延ばしたいという箇所を、中途半端に詰めておかねばなりませんでした。そうした心残りの箇所を、この改訂版では、みな満足のゆく分量にまで、拡大しています。
さらに幕切れの箇所ですけれども、…… 音楽はオリジナル版は、静かな箇所が付いて終わったのです。
…… 音楽としてもどうも格好が悪いので、この改訂版では、当初の意図通り、サロメが潰され、一気に幕のかたちにしてあります。
ところで小倉朗だが、純音楽作品以外では、数多くのTV音楽などを書いてある。
NHKの契約作曲家となったからだ。
「ビルマ語の時間」の音楽とか「テレビ体操」への主題音楽とか……
昔の話で、いつまで使われていたのかわからない。
私も知らない。
 私が若杉弘指揮のコンサートを聴くことができたのは1回だけだ。たぶん。男らしく断言するには記憶がけっこうあいまいだけど……
私が若杉弘指揮のコンサートを聴くことができたのは1回だけだ。たぶん。男らしく断言するには記憶がけっこうあいまいだけど……
札響の定期演奏会で、プログラムはマーラー(Gustav Mahler 1860-1911 オーストリア)の交響曲第9番ニ長調(1909-10)で、この“第九”に関しては私にとって現在に至るまで唯一の“ナマ体験”である。1996年のことだ。
ちなみに、今年札響は尾高忠明の指揮でこの曲をやる(10月)。
コンサートではそこそこ感動した。そこそこというのは、終楽章でオーケストラのあるパートが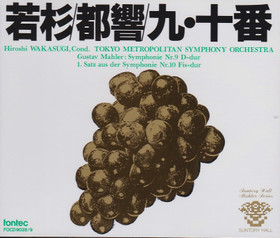 ズレてしまったからだ。あれ、けっこう痛かった。
ズレてしまったからだ。あれ、けっこう痛かった。
この日の演奏は、後日FM北海道(Air-G)で放送され私はそれを録音したが、けっこう弦の音にザラツキがあるのに驚いた。また、若杉がアナウンサーのインタビューに「マーラーばっかりやってると、オーケストラの音が荒れる」とも言っていた。
若杉/都響の“「第九」を聴いて、不思議なことにカセットテープに収めた札響との演奏の記憶が蘇った。
札響の演奏をはっきり覚えているわけではない。いや、すっかり忘れてしまっている。カセットテープももう無い。
が、このCDから出てくるのは、まぎれもいなく、あのときと同じ響きだ。
これが若杉スタイルか……
変なところで感心してしまった私。
そして、若杉のマーラー指揮者としての評価がようやっと、少しは理解できた気がする。
この第9番は、曲の性格もあるのだろうが、私の知る若杉のマーラーのライヴのなかでもとても良いものだ。
中間の2つの楽章にはややすっきりしすぎの感があるが、両端のテンポの遅い楽章はじーんとくる。味わい深い感動的な演奏だ。
1991年ライヴ。フォンテック。
さて、ブログのお引越しの準備だが、いまこれとこれの2つをお試し中である。
あぁ、迷える子羊状態。
みなさん、どう思います?
ですから、どっちを採用すべきかという点で。
ただ、いずれにせよ“ブログ人”のこれまでの記事はgooブログに転居させなければならない。“ブログ人”で用意される予定のお引越しツールを使うしかないわけだ。
問題は“ブログ人”閉鎖後の新規記事をgooとlivedoorのどちらのサービスを利用するかということだ。
いや、自分のなかではだいぶ気持ちは傾いてきている。どっちかって?まだ、内緒。
今日は午後から出張である。
悩みを抱えたまま旅に出る私。
 緊急地震速報のチャイム。
緊急地震速報のチャイム。
警告音というほど強くなく、また無機質でもないが、独特のただならぬ気持ちにさせられる。
ご存知の方も多いと思うが、このチャイムを作ったのは伊福部達(1946- )。伊福部昭(Ifukube,Akira 1914-2006 北海道)の甥にあたる人だ。
そしてまた、一部で誤って伝わっているのが、このチャイムのもととなったのが「ゴジラ」の音楽だということ。正しくは、「ゴジラ」ではなく「シンフォニア・タプカーラ」からこのチャイムが作られたのである。
そのあたりは、筒井信介著(伊福部達監修)「ゴジラ音楽と緊急地震速報」(ヤマハミュージックメディア)に詳しいが、チャイム音は「タプカーラ」の第3楽章の冒頭の和音が素材となっており、それを伊福部達が選んだのは、“適度な緊張感”と“インパクト”を持っているからだという。
生体工学、音響工学、福祉工学を専門とする伊福部達がNHKからチャイム制作を依頼されたときに、チャイム音に求められる条件としてあげたのは次の5つだったという。
・ 注意を喚起させる音であること
・ すぐに行動したくなるような音であること
・ 既存のいかなる警報音やチャイム音とも異なること
・ 極度に不快でも快適でもなく、あまり明るくも暗くもないこと
・ できるだけ多くの聴覚障害者にも聴こえること そして、「タプカーラ」第3楽章の冒頭のジャンッ!の和音を分解、アルペジオ的にチャイム音を作り出し、さらに音楽的要素を薄めてチャイム音としての機能を高めたのだそうだ。
そして、「タプカーラ」第3楽章の冒頭のジャンッ!の和音を分解、アルペジオ的にチャイム音を作り出し、さらに音楽的要素を薄めてチャイム音としての機能を高めたのだそうだ。
その「シンフォニア・タプカーラ(Sinfonia Tapkaara)」(1954/改訂'79)を、今日は本名徹次/日本フィルの演奏で。
キングの「伊福部昭の芸術8 特別編 頌 ― 伊福部昭 卆寿を祝うバースデイ・コンサート」のアルバムで、2004年のライヴ。ここに収められているのは第3楽章だけである。
これまた白熱したすばらしい演奏。
最後の音が終わるや否や、会場に絶叫に近いブラボーが飛び交うのも納得がいく。
上に書いたことでご承知のことと思うが、「タプカーラ」からあのチャイムのメロディーが聴こえてくるわけではないので、念のため。
 将来-といっても今年の秋のことだ-の“ブログ人”サービス終了に備え、まずはgooブログに登録した。まだ無料版にとどめている。
将来-といっても今年の秋のことだ-の“ブログ人”サービス終了に備え、まずはgooブログに登録した。まだ無料版にとどめている。
なんだかOCNが推奨するからといって、言われるがままにgooに移行するのははっきり言って癪だ。けど、テクニカル面でそんなに知識が無い私には、推奨先以外に切り替える自信がこれっぽっちもないと自信をもって言える。また、テクニカル面であまり知識がないと書いたものの、テクニカル面以外では何ら問題がないほど知識があるかと問われれば、これまた「無い!」と胸を張って言える。
このブログの最近の記事をgooブログにも載せたが、まずもって自分でしっくりくるテンプレートが見つからない。gooのテンプレートの数は実はブログ人より多い。だから、たぶんそのうちしっくりくるものが見つかるか、見慣れてしっくり感じるようになるのかもしれない。が、それには何度も選び、とっかえひっかえ表示させ、やっぱり気に入らないという経験を涙があふれるくらい繰り返さなきゃならないだろう。そう考えるだけで、気持ちが重くなるし、そこまでして続ける意味合いがあるのだろうかとも思ってしまう。
OCNはせめてもの罪滅ぼしで、ブログ人のテンプレートをgooのテンプレートに移譲してくれんだろうか?そんなはかない願いを心に抱いている。
まだ全然慣れないので、写真の入れ方もよくわからない。が、サイズ指定ができないようで、これまたまいった。
現在のカテゴリーがどうなるのかもさっぱりわからない。右も左もわからない砂漠に投げ出されたような気分だ。
とにかく初めて北海道の田舎町から東京に移り住んだ身寄りのない老人のような心境だ。
そんなことやら愛想っ気のないマーラーなんかを聴いてきたりで、ストレス発散とばかりヨッフム/シュターツカペレ・ドレスデンによるブルックナー(Anton Bruckner 1824-96 オーストリア)を久々に聴いた。
曲は交響曲第8番ハ短調WAB.108(1884-87/改訂1889-90)。使用楽譜は1890年稿ノヴァーク第2版。
これ、一糸乱れぬ演奏ではない。が、熱く燃える入魂の輝きが興奮をもたらす。胃もたれしない適度な濃厚さ。溢れんばかりの生命力。私は10日ぶりに水を与えられた観葉植物のようになった。
やはりヨッフムのブルックナーはすばらしい。
1976録音。ワーナー。
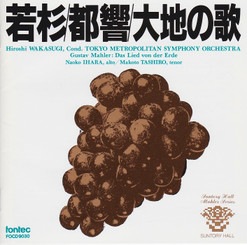 それは先週の今日のことだった。
それは先週の今日のことだった。
いつもニコニコ現金払いをしているかかりつけの病院で、予想に反して私が新たなおビョーキを抱えていると宣告されたのは。
男らしくなく、「本当にそうなのだろうか?もう一度検査をすれば正常値ということが証明されるのではないだろうか」と私はいまだに思っている。
しかし、とにかく、これまでの高中性脂肪、高血圧、高尿酸血症に加え、境界型糖尿病というものが私の体に仲間入りした。歓迎していないのに……
この1週間悶々とし、考えた。
が、考えてもしょうがない。すっきりするために、今日の13日の金曜日に、思ったことを書いて悶々とした気分を発散し、ムンムン気分になろう。
人間ドックで膵管拡張が発見されたのは2010年のこと。CT検査と超音波内視鏡検査を受けた。
結果はシロだった。
翌2011年のドックでも膵管拡張が指摘され、CT検査を受けた。
結果はシロだったが、膵臓表面がざらざらしているとわけのわからんことを言われた。わけがわからんというのは、それが正常なのか異常なのか、多様な事例の1つに過ぎないのか説明されなかったからだ。また、そのとき医者は私の飲酒状況を聞き、予言者のように「汝、いずれ膵炎になるだろう」と言った。
2年後にまた来院するようにも言われたが、その後私は転勤したので予言者の言葉を無視したままだ。
が、小心者の私はただ転勤したから行くのを止めたというのではない。
ここ転勤先で受診したドックでは、12年も13年も、そして今年も膵管拡張は指摘されていない。
見落とされているのだろうか?いや、3年続けて見落とすなんてことはないだろう。ただ気がかりなのは、脂肪肝が邪魔してエコー検査で膵臓が見えにくくなっている可能性がないとは言えないということだ。
仮に膵臓が弱っているとなると、インスリンの分泌が満足に行なわれなくなり、糖尿病になる可能性がある。
また、もともとかなりの高水準にある中性脂肪は膵炎を起こす危険性をもっている。
となると、遺伝に加えこれらが絶妙にリンクして糖尿病面で徐々に私を正常から境界型へ誘導したのではないかと、疑いを抱いてしまう。
ただ、まだ1ヵ月半ほどだが、主食を減らすことによって体重が4kgほど落ちている。
ということは中性脂肪の値も下がってくれていることが期待できる。先週も採血したが結果は次回聞くことになっている。正直なところ、早く知りたい。
値は間違いなく下がっているはずだ。そうでなければ、炭水化物節制ダイエットの効果はあらゆる数値を改善するという、その手の本の説を私1人のせいで否定することになってしまう。
だが、もし相変らず中性脂肪の値が下がってなかったら、私にはもう安直な対応策がない(酒を制限するのは安直とはまったく言えない、無理な相談というべきもの)。
それが1週間考えていたことだ。
こう書いてしまうと、実にたいしたことないことを考えていたものだ。
酒にまつわる曲としてマーラー(Gustav Mahler 1860-1911 オーストリア)の「大地の歌(Das Lied von der Erde)」(1908-09)。全6楽章のうち第2楽章と第4楽章を除く4つの楽章の歌詞に酒やら杯が出てくる。
第1楽章の歌いだしは「黄金の杯を満たす美酒」と言いながらも「飲む前に1曲歌おう」とお預けをくらわす。最後には「杯を底まで飲み干せ」と強要。急性アルコール中毒を起こしたらどうするんじゃい?
第3楽章では着飾って飲ミニケーションしてるし、第5楽章ではデロデロになるまで酔っぱらい、終楽章では友と別れの盃を交わす。
さて、本日も若杉弘/東京都響の演奏を取り上げる。
独唱はアルトが伊原直子、テノールが田代誠。
1991年ライヴ。
第3番や第4番、第6番では、どこか他人行儀で欲求不満が残る、アタイをイライラさせたいのかい?という若杉だったが(T.Tさんのコメントに納得させられた)、「大地の歌」は録音でもなかなか良い演奏だ。
この曲が、マーラーのものとしては響きが重層的ではなく室内学的なところが多く、またこの世は無情だわいという性格なために、若杉の丁寧なアプローチがマッチしているのだろう。
オーケストラも繊細で美しく、歌手2人もややがなってるかなと感じるところもあるが、ドラマティックな歌唱。このあたり、オペラ指揮者としての若杉の本領発揮というところ。
日本人指揮者による「大地の歌」としては高水準と言えるのではないだろうか?
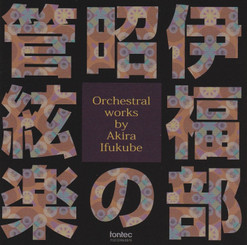 日曜日の夜、肉とシメジを炒めて食べようと思ったが、さて、味付けはどうしたものかと迷った。
日曜日の夜、肉とシメジを炒めて食べようと思ったが、さて、味付けはどうしたものかと迷った。
ポークジンジャー風にするのもいいが、そして生姜焼きの味は突然いつ食べても美味しいが、いつもいつもじゃちょいと芸がない。
豚丼のタレが冷蔵庫に残っているからそれを使うことも考えたが、この日の私は甘辛い味付けを求めていなかった。だって、境界型、めったに間食しないのにこのときは夕方に餡の串団子を食べちゃったし……
中華風にしようか?でもなぁ……
そんなときに唐沢寿明が私に訴えた。TVの中から。
ミツカン味ぽんだけでとっても美味いと。
コマーシャルでは豚肉とタマネギだけを炒めているようだったが、野菜室の中のシメジをなんとか本日中に使い切りたかったので、豚肉とシメジとタマネギを炒めることとした。
味ぽんだけというのは、調理人(本日の)としては芸がないので、①コショウを振り、②おろしショウガを少し入れ、③酒もちょいと加え、④最後に味ぽんを入れて仕上げた。たいした芸でなくてすまんけど。
うん、なかなかいけた。
唐沢さんはウソついてなかった。
ただ4種の調味料のうち、最初の3つの効果がどの程度か不明。最後の1つ、味ぽんだけでも十分かもしれない。
伊福部昭(Ifukube,Akira 1914-2006 北海道)のヴァイオリンと管絃楽のための作品、現在はヴァイオリン協奏曲第1番と呼ばれるものには、4種の版がある(あった、というべきか)。
伊福部は作品を改訂することも少なくなかったが、3回も改訂をするのは異例のことだ。
1948年に「ヴァイオリンと管絃楽のための協奏曲」が書かれた。自らがヴァイオリンを弾いていた伊福部にとって、その楽器をソロにした最初のコンチェルトである。
この曲は3つの楽章から構成されていたが、1951年に第2楽章をカット。2楽章構成の「ヴァイオリンと管絃楽のための狂詩曲」とした。
さらに1959年に改訂し「ヴァイオリンと管絃楽のための協奏風狂詩曲(Rapsodia concertante per Violino et Orchestra)」となった。
2回目の改訂から12年経った1971年に現在演奏される形に直されたが、曲名は1959年と同じ「協奏風狂詩曲」。だが、カッコ書きで「ヴァイオリン協奏曲第1番」という名が付されるようになった。
このあたりの経緯は、先日紹介した“伊福部昭 文藝別冊”に詳しく書かれている。
このたびフォンテックから出たCDには1959年版の演奏が収録されている。
NHKがラジオ放送用に録音したもので、独奏は小林武史、森正指揮ABC交響楽団の演奏である。
第1楽章は現在の版(1971年版)とあまり変わらないが、第2楽章はけっこう違いがある。こちらの方がより土俗的だ。貴重な音源であることは間違いないが、音楽としては慣れのせいもあるのだろうが、私は今の形の方が好きだ。
1959録音。モノラル。
NHKのアナウンサーによる伊福部昭へのインタビューも収められている。
なお、このコンチェルトの第1楽章に出てくるメロディーが、のちにゴジラの音楽となるものの原型である。
- 今日:
- 昨日:
- 累計:
- 12音音楽
- J.S.バッハ
- JR・鉄道
- お出かけ・旅行
- オルガン曲
- ガーデニング
- クラシック音楽
- コンビニ弁当・実用系弁当
- サボテン・多肉植物・観葉植物
- シュニトケ
- ショスタコーヴィチ
- スパムメール
- タウンウォッチ
- チェンバロ曲
- チャイコフスキー
- ノスタルジー
- バラ
- バルトーク
- バレエ音楽・劇付随音楽・舞台音楽
- バロック
- パソコン・インターネット
- ピアノ協奏作品
- ピアノ曲
- ブラームス
- プロコフィエフ
- ベルリオーズ
- マスコミ・メディア
- マーラー
- モーツァルト
- ラーメン
- ルネサンス音楽
- ロマン派・ロマン主義
- ヴァイオリン作品
- 三浦綾子
- 世の中の出来事
- 交響詩
- 伊福部昭
- 健康・医療・病気
- 公共交通
- 出張・旅行・お出かけ
- 北海道
- 北海道新聞
- 印象主義
- 原始主義
- 古典派・古典主義
- 合唱曲
- 吉松隆
- 名古屋・東海・中部
- 吹奏楽
- 周りの人々
- 国民楽派・民族主義
- 変奏曲
- 多様式主義
- 大阪・関西
- 宗教音楽
- 宣伝・広告
- 室内楽曲
- 害虫・害獣
- 家電製品
- 広告・宣伝
- 弦楽合奏曲
- 手料理
- 料理・飲食・食材・惣菜
- 映画音楽
- 暮しの情景(日常)
- 本・雑誌
- 札幌
- 札幌交響楽団
- 村上春樹
- 歌劇・楽劇
- 歌曲
- 民謡・伝承曲
- 江別
- 浅田次郎
- 演奏会用序曲
- 特撮映画音楽
- 現代音楽・前衛音楽
- 空虚記事(実質休載)
- 組曲
- 編曲作品
- 美しくない日本
- 舞踏音楽(ワルツ他)
- 行進曲
- 西欧派・折衷派
- 読後充実度
- 邦人作品
- 音楽作品整理番号
- 音楽史
- 駅弁・空弁
© 2007 「読後充実度 84ppm のお話」

