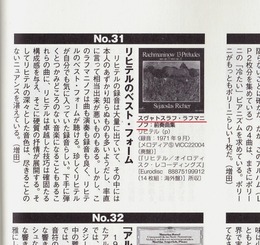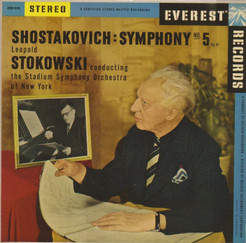質屋を見てF.W師を思い出す
質屋を見てF.W師を思い出すF.Wというのは Wilhelm Friedemann Bach のことではない。そうならW.Fだもん。
F.W師というのは、私が中学生のときに通っていた学習塾の数学の先生のことだ。
単なる先生ではない。主宰者であった。
大手の塾ではない。単独の独立系超弱小学習塾であった。
F.W師もこれが本業。
詳しくは知らないが、大学時代にここで講師としてバイトをし、そのまま主宰者になってしまったということだろう。
正職といえば正職だが、フリーターといえばフリーターである。
F.W師は四国出身で、憧れて北海道の大学に入った。
四国の人がすべてそうかどうかは知らないが、師はいち、にぃ、さん、しぃ、ごぉ、ろく、ひち、はち……と、7のことを“しち”と言えなかった。4は“しぃ”と言えるのに不思議である。
この地で看板を見て、F.W師のことを思い出したのだった。
ただそれだけ。
で、編曲したのは誰?
“ひち”関連でハイドン(Franz Joseph Haydn 1732-1809 オーストリア)の「十字架上のキリストの最後の7つの言葉(Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuze)」。
 この作品は、管弦楽作品として1785年に作曲されたが(Hob.ⅩⅩ-1a)、その後弦楽四重奏曲(第50~56番。Op.51/1787)とオラトリオ(1794)に編曲されている。
この作品は、管弦楽作品として1785年に作曲されたが(Hob.ⅩⅩ-1a)、その後弦楽四重奏曲(第50~56番。Op.51/1787)とオラトリオ(1794)に編曲されている。今日はクラヴィーア(ピアノ)版を。
このCDの帯には、この版についてはハイドンが“監修”したと書かれている。
詳しいことはわからないが、ということはオラトリオや弦楽四重奏曲とは異なり、ハイドン自身による編曲ではないということだろう。
ヤンドーの演奏で。
↑ ヤンド